電話・睡眠・死都・調布(特別対談・後編)
取材・文=松永良平
──後半は、川勝さんの話をしていきましょうか。ここまでは斎藤さんのファンであり、漫画雑誌『架空』『蝸牛』の編集者としての立場からの発言も多かったですけど、もちろん自身も漫画家です。そして、一般流通の単行本としては初となる作品集『電話・睡眠・音楽』発売のタイミングでもあり。
もともと僕は川勝さんの名前を、小西康陽さんを通じて知りました。小西さんがピチカート・ワン名義でリリースしたセカンド・アルバム『わたくしの二十世紀』(2016年4月)がLPレコードになる際に、もともとCDでは写真だった雪景色を油絵に描き換えたのが川勝さん。その後、クラブやライヴハウスでばったり会う機会も多かった。知り合ってみると、歳も若いし、描いている漫画も一筋縄ではとてもいかないものだったので、さらに驚いて興味を持って。まずは、そもそも漫画を好きになって、漫画家になっていったいきさつから話を聞いていきたいです。
■川勝 小学生のときに初めて漫画を描いたんですよ。(漫画を描くのが)学校で流行ってたんです。塾で配布されるプリントを整理するクリアファイルに間仕切りの色紙が入っていて、それを捨てるのがもったいないから、二つに折って漫画を描いていたのです。
最初に描いたのは「デスのび太」という漫画でした。のび太が母親や先生をひたすら殺していくハードボイルド漫画です(苦笑)。すごく絵が下手で、自分でもげんなりしました。でも、おじさんだけ描くのがうまかったかな。
■斎藤 へえ。おじさんを描くのって、わりと難しいというか。
──とはいえ、その時期の漫画は、単純に遊びの一環ですよね。
■川勝 漫画は好きでしたけど、むしろ最初はクラシック音楽のほうに興味あったんです。神保町や高田馬場にレコード屋目当てで行くようになって。さらに古書市に行くようになると小説を買ったり、漫画を買ったりと、周りにあるものに趣味が伝播していくじゃないですか。それで古い漫画をよく読むようになっていきました。
──才能がすごくある人だというのはちょっと話してもわかるんですけど、そこから漫画に行った、というのはどういうきっかけで?
■川勝 「なぜ漫画家をやろうと思ったか」という意味ですか? 今、僕は26歳ですが、ちょうど四年くらい前は就職率がまだ悪かったんですよ。僕は大学院に進学したのですが、卒業してそのまま就職した同級生の中には、薄給で、身体も壊して会社をやめるという人がかなりいた。彼らの給与も驚くほど少なかったので「漫画家って職業もアリかもしれないぞ」と思ったんです。「漫画を描いてゲット・マネーするのも悪くない」と。そう思ったのは大きいですね。
──そのとき作ったのが、最初の単行本として自主制作した『十代劇画作品集』(2012年)?
■川勝 いや、あれはもっと前で大学生のときです。大学院のころ自分の作品を持って売り込みに行ったことがあります。でも、まず一社行ったらぜんぜん合わなくてね。編集者に“ツイッターのホラー漫画界隈のめんどくさいやつ”扱いされました(笑)
■斎藤 どれ持っていったの?
■川勝 「不憫な奴」(『架空』15号初出)ですね。ホラー漫画だったら金になるかなと思って、2週間くらいで描いたんです。ジャンルものならいけるかなと思ったらダメでした。
──ちょっと待ってください。じゃあ、『十代劇画作品集』の時点では、漫画家になるつもりはなかった?
■川勝 僕はアンダーグラウンドの人なんで、基本的に漫画ではメシは食えないんですよ。だから、就職はしなくちゃいけないと思ってました。『ガロ』に描いてた作家の人たちだって、漫画では食えてなかったと思うし。
■斎藤 でもさ、たとえば俺は漫画で食いたくても食えないだけで、川勝くんみたいに最初から漫画で食うつもりがない、ってわけじゃない。
■川勝 え? そうなんですか?
■斎藤 普通に「(漫画で)お金は欲しいな」って思うよ(笑)
■川勝 ガロに載っているようなスタイルの漫画を出版社に売って稼ぐのは難しいなと思っていて、もし稼ぐならお金になる作風に変えますよ。作風を変える気はなかったから、漫画で食うのは無理だろうと判断してました。
【「十代劇画作品集」】
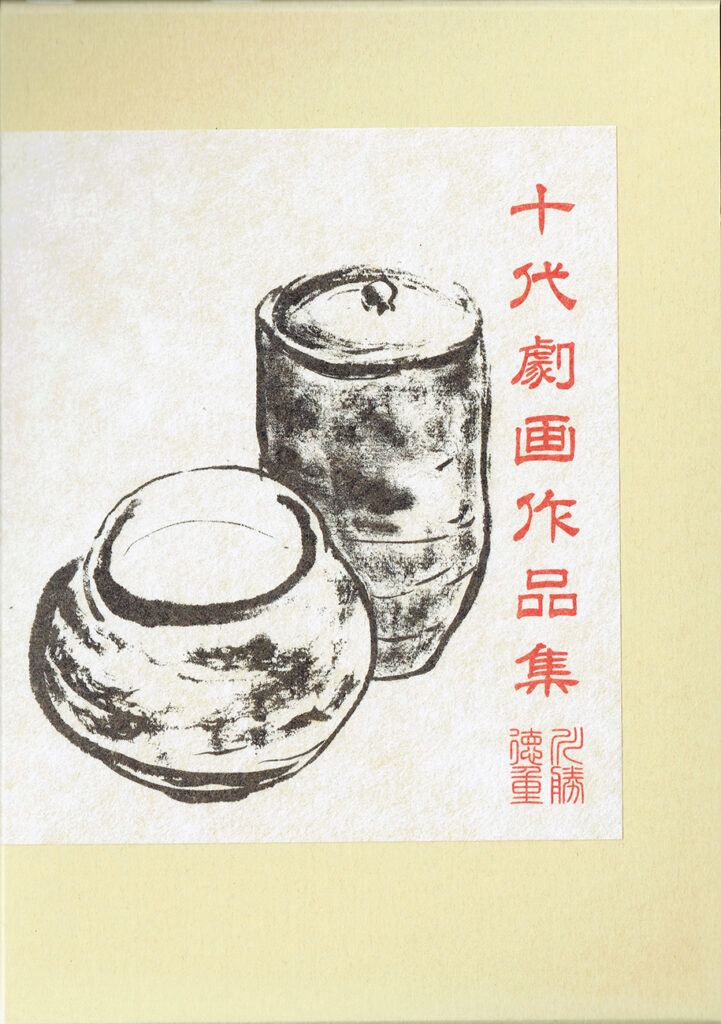
【「不憫な奴」】

【『架空 15号』

──『架空』の編集を西野さんから任されるようになったことで、漫画家という職業への意識が変わった、というのは、ないですか?
■川勝 職業という点では、あまりないですね。正直言うと、僕はまだ「漫画メインでは食えないから、これ以外の仕事をしなくちゃいけない」っていう気持ちは変わってないです。だけど、大学も出ちゃったし、どうしよう? みたいな感じです。
──とはいえ、“バズった”という言い方が正しいかどうかはわからないけど、今回の単行本の表題作である「電話・睡眠・音楽」が、『トーチweb』に発表されたとき(2016年9月)、明らかにネット界隈がざわつきましたよね。それまでの川勝さんの漫画を知ってた人たちからしても、あの作品は題材や空気感が明らかに現代で驚いたと思うけど。とにかく、あれで注目した読者はすごく多いですよね。
■川勝 (依頼が来たとき)僕は水木しげる風の作品が得意だったんですけど、『トーチweb』の執筆陣を見たときに、水木路線だとドリヤス工場さんがいたし、もうちょっと劇画寄りにしても田中圭一さんがいた。だとすると、ここで自分を売るには作風を変えないといけないなと思ったんです。それで、僕は洋物の漫画が好きだけど、それはみんな認知してないだろうと思って、あれを描いたんです。
──洋物ということは、グラフィック・ノヴェルとか、バンド・デシネとか?
■川勝 あと洋画とか。ヨーロッパものが多いです。
──これも小西さん経由で当時知った情報ですけど、小西さんは川勝さんとは“名画座に足繁く通う若者”として知り合ったといういきさつがありますよね。
■川勝 本当に大学時代はひまで、何もすることがなかったんですよ。だから映画ばっかり見てました。話の合う同級生はみんな大学をやめるか、休学してしまったので。
──ピチカート・ワンのジャケットのイラストも、そういう縁から担当することになったんですよね。
■川勝 小西さんと2日か3日連続で席が隣になったことがあったんです。名画座って指定席じゃないんですけど、勝手にみんな指定席を決めてるんです。池袋の新文芸坐で、僕はいつも前から4番目でした。でも、あるとき席を前から3番目にしたら、小西さんと続けざまに隣になったんです。それで、僕は小西さんのファンだったんで話しかけました。たしか、有馬稲子特集のときだったかな。
──そのときは「漫画を描いてるんです」って自己紹介をしたんですか?
■川勝 そうです。あと、「僕、ピチカート・ワンの『11のとても悲しい歌』(2011年)を聴いてます」って。漫画を描いてる話をしたときに、僕が「北冬書房」って名詞を出したら、小西さんがびっくりして「あ、高野慎三」って仰ってました。それから、『夜行』とか、つげ義春選集の話、小西さんが青林堂に行った話などしました。そういうやりとりがきっかけでよく話をするようになったんです。
【ピチカート・ワン「わたくしの二十世紀」/ジャケットイラスト=川勝徳重】

──「電話・睡眠・音楽」の舞台には、小西さんがよくDJをしている渋谷のオルガンバーも描かれてますけど、それもその出会いがきっかけ?
■川勝 ああ、そうですね。ただ小西さんと知り合ったのは大学生の頃だったので、「電話・睡眠・音楽」の直接のきっかけではないです。
むしろ描くことになった直接のきっかけは、意志強ナツ子さんの勧めで〈コミティア〉の出張編集部に行って、そこで編集の中川敦さんに会って『蝸牛』を渡したことです。そのあと、元カノが山田参助さんファンだったので、参助さんのサインを代わりに貰いに「トーチ五輪」という渋谷アップリンクのイベントに行ったときに中川さんに再会しました。「何か(『トーチweb』に作品)持ってきてよ」って言われたんで、「じゃ、ヌーヴェルヴァーグやります。」って言ったんです。
■中川 それから1年以上待つことになりましたが、原稿が上がってきた時は「おお」と、なりました。ドリヤス工場さんや田中圭一さんと違う路線を目指すからといって、即座に「じゃあヌーヴェルヴァーグで」とは普通ならないと思います。ヌーヴェルヴァーグというキーワードは、その時点で川勝くんの中ですでに熟成したものだったんじゃないかと。
■川勝 僕の持ち駒で戦えるものとして考えたとき、これだったんです。
■斎藤 持ち駒って考え方がすごいよね。俺はこれ(『死都調布』を指し)しかないから(笑)
■川勝 だから、そこが僕のよくないところで、作家性の無さなんですよ。いつも、持ち駒とかそういうことを考えちゃう。編集もやってるから、そういう判断をしてしまうんです。
──僕は川勝さんは十分すぎるくらい作家性はあると思いますよ。ただ、作品主義なだけで。その作品主義があったからこそ、「電話・睡眠・音楽」があがってきたわけですもんね。
■中川 「左びらきで」とも言ってましたね。
■川勝 フランスの漫画家にフレデリック・ボワレがいます。彼が日本で出版した単行本『恋愛漫画ができるまで/フレデリック・ボワレ短編集』(美術出版社)は、前と後ろからどちらからでも読めます。右びらきと左ひらきの漫画が両方掲載されているのです。この本は最初から念頭にありました。
【『怪奇短編劇画集 蝸牛』】

【『恋愛漫画ができるまで/フレデリック・ボワレ短編集』】

──バンド・デシネとヌーヴェルヴァーグ、そしてオルガンバーが重なっていったのは不思議な流れですね。
■川勝 いや、不思議じゃないんですよ。昔、『劇画の歴史』(ジェラール・ブランシャール著)という本が日本でも出てたんですけど、それは中身がフランスのバンド・デシネの歴史についての話だったんです。バンド・デシネの歴史の本を「劇画」と訳すのは無理があるけれども、言わんとしていることはわからないでもないです。ヌーヴェルヴァーグ映画が出てきたのが1958、9年くらいで、日本で辰巳ヨシヒロが「劇画宣言」をしたのも59年。50年代後半は戦後の若者文化がバッと出たのがその頃なんで、つながるものはあるかなと。
──なるほど。でも、川勝さんが「電話・睡眠・音楽」を描いたのは21世紀の2016年。
■川勝 僕は、その時代にすごく憧れがあるんです。そういうことをずっと考えてたので、その影響が漫画に出たのか、そこはよくわからないですけど。
■中川 たしかゴダールの関連書籍の解説文で日本の映画監督がこんなことを書いていました。「私がヌーヴェルヴァーグの作家たちから教わったのは、パクれ、切り貼れ、それでいい、じゃんじゃんやれ、ということで、映像を志す若い世代がこのメッセージにどれだけ勇気付けられたことだろう」と。どの本で誰が書いていたか記憶が不確かで申し訳ないのですが、そういうことが書かれていたのを、今回の単行本(「電話・睡眠・音楽」)の制作過程で思い出しました。
■川勝 (ヌーヴェルヴァーグの担い手たちは)アーカイヴを持てた最初の作家たちなんですよ。アンリ・ラングロワのシネマテークで映画を浴びるように観たり、自主上映会を催したり…。トリュフォーやゴダールとか若い映画狂たちがみんなアンドレ・バザン(ヌーヴェルヴァーグの作家たちの精神的支柱となった批評家)のもとに集まって映画評論をやってた。彼らは最初に評論をやってて、それから映画を撮っていった。何度もアーカイヴとしてフィルムを観ながら参照して、また撮って。当時、普通の人たちはそんなふうにフィルムを何度も観るなんてできなかったと思うけど、あの人たちにはできたんですよ。
──そういう引用や編集の感覚はヒップホップとかサンプリングを通じて、90年代以降の音楽にも通じていきますよね。
■川勝 それで思い出したことがあります。音楽の人は、サンプリング文化を通ってきています。僕が最初に漫画を描いてた十代のころは、よく「古い漫画だ」ってディスられてたんです。漫画好きの人にも、編集者にも、漫画家にも言われてました。「なんでこんなつげみたいな作風なんだ?」みたいな(笑)。だけど、音楽のほうに行くと、たとえばインディー・バンドが「ビートルズがめっちゃ好きで、60年代っぽくやります」って言っても、怒られないじゃないですか。漫画家はそれが逆なんですよ。細野晴臣の新譜『Vu Ja De』(2017年)は二枚組のアルバムで、1枚目はカヴァー、2枚目がオリジナル曲という作品集でしたが、そういうことをする作家が漫画界にはいないですね。とにかくウケが悪かった。
──映画って、引用に対していかに柔軟であり饒舌であるかということがすごく大事だし、どんなにジャンル違いに見える映画でもテンポ感や編集の手法、物語の構成なんかは綿々と受け継がれてきたものですからね。
■斎藤 『死都調布』で、わからないように映画から引用してるところは結構あるんですよ。ジム・ジャームッシュの映画に『ゴースト・ドッグ』(1999年)ってのがあって、主人公は殺し屋でフォレスト・ウィテカーがやっていて、音楽はヒップホップが使われてるんです。あと、すごくおもしろいと思ったのが、ところどころで『トムとジェリー』みたいな昔のアニメ映画が、子供が見てるって設定で挿入されるんですけど、「爆弾を投げてボーン!」ってアニメのシーンが挿入されたあとで、現実でも爆弾が爆発するシーンがあったりする。「引用して、韻を踏む」みたいな、ヒップホップ的手法を映画のなかでもやってるんですよ。その引用は、『死都調布』でもやりました。まあ、うまくできてないですけど(笑)
でも、よく映画好きの作家とかで、映画のシーンのパロディみたいなのをやっちゃう人がいる。そういうふうにしたくないんで、引用だとわからないようにはしてるんです。映画オタクで漫画描いてる、みたいにはしたくない。
──「電話・睡眠・音楽」に話を戻しますけど、あの作品で僕が好きな描写は、深夜のクラブの暗さとか、居場所のない感じがちゃんと描かれてるところなんです。普通に漫画やドラマ表現のなかで扱われるクラブって、明らかにパーティーで盛り上がってる場所だったりすることがほとんどじゃないですか。
■川勝 (そういう表現をする人たちはクラブに)行ったことないんじゃないですかね? 盛り上がってる部分だけを描いているというより、クラブという場を記号的に描いているだけなんだと思います。
■斎藤 俺もクラブって行ったことないけど、今はこういうのが普通なの? みんな踊ってて、派手な格好してて、トイレでドラッグの売買してる、みたいなのじゃないの?(笑)
■川勝 それっぽい空気のところもあるかもしれないけど、少ないですよ。
■斎藤 じゃあ、みんなクラブで何やってんの?
■川勝 酔っ払って踊ってるんじゃないですか?
■斎藤 ただ酔っ払ってるの?
──やり過ごしてる時間を描くというのは、すごく難しいじゃないですか。それができてる稀有な例だと思ってます。
■川勝 やり過ごしている時間を描く例は、たとえば他ジャンルをみれば結構あるんじゃないでしょうか。村上春樹の『アフターダーク』(2004年)も一夜を描いた小説ですが、そういう無為な時間が表現されてますし、村上がこの小説を書くときに念頭に置いていたというロベール・アンリコ監督の『若草の萌えるころ』(1968年)もそういう傾向が強い映画です。ただアンリコ監督のはアッチ行ったりこっち行ったり、意外とワチャワチャした映画でしたが。「やり過ごしている時間を描く」というのはキャラクター主義では中々描きにくい主題じゃないでしょうか。
──そういう意味では『死都調布』もキャラクター主義、主人公ありきの漫画じゃないですよね。
■斎藤 主人公のいる作り方だと奥行きがない気がしちゃって。もっと俯瞰した視点で、いろんな人の対比が見えるような漫画にしたい感じなんです。
──登場人物に感情移入するスキがないですからね。この人どうなるんだ? ってハラハラする気にさせる前に死んじゃうみたいな。
■斎藤 俺自身も感情移入しないで描いてますから。
■川勝 僕も斎藤さんも、登場人物への思い入れがないから(笑)
■斎藤 ないない(笑)
──そこを新しさと言っていいかどうかはわからないけど、今の漫画にないところかも。
■斎藤 新作では、『死都調布』みたいな一話完結じゃなくて続き物に挑戦したいんです。そうすると、登場人物をある程度固定しなくちゃいけないんですけど、キャラクター主体にならないように登場人物をどうバランスよく配置していくかっていうのがすごく難しいんです。
■川勝 斎藤さんは、デビュー作からそもそもの考え方が違うし、本気で「キャラクター漫画描いてセルアウトするぞ」って思ったとしても、みんなとおなじような漫画にはならないから、ぜんぜん大丈夫ですよ。
■斎藤 そう? みんな、ああいうキャラクター漫画は描きたくないのに出版社の都合で描かされてるんじゃないの?
■川勝 違いますよ、みんな描きたくて描いてるんですよ。
■斎藤 そうか、みんな、そういうのが好きなんだ! そうかそうか。
──川勝さん、「電話・睡眠・音楽」を発表してから、あれみたいなのをまた描いてほしい、っていうオファーは結構あったでしょ?
■川勝 ありましたね。それで描いたのが『Switch』に描いた「冬の池袋、午後5時から6時まで」。その後に「電話・睡眠・音楽」の池袋版をやろうとしたんだけど、僕のなかの要求がいろいろ高くなりすぎて、あれはちょっと挫折しました。ジャック・リヴェットに『パリはわれらのもの』(1961年)ていう変な映画があるんですけど、ああいう不穏な緊張感が描きたかったんですけどね。
【「冬の池袋、午後5時から6時まで」】

──今回の単行本リリースを経て、新作についてはどう考えてますか? 斎藤さんは描き始めているというお話でしたけど。
■斎藤 『死都調布』の続編を描いてます。『死都調布 南米紀行』ってタイトルだけ決めて。あんまり俺、旅行とか行ったことないんですけど。
■川勝 いや、行ったらダメですよ。描けないですよ。
■斎藤 描けないのかな?(笑) まあ、いろいろ考えちゃうと難しいですね。『死都調布』が出版されてから、いろいろ感想を書いてくれてる人たちがいるんですけど、「褒めてくれてるけどなんか違うんだよな」みたいに思うことも結構あるし。
でも、漫画家は続けたいですけどね。俺はこれしかないから。子供の頃から、絵以外で褒められたことないんですよ。
■川勝 絵は褒められてたんですか?
■斎藤 小一のときに図工で描いた絵を先生が勝手に市のコンクールに応募してて、二年生になったときに、朝礼で校長先生に前に呼ばれて表彰されたの。相模原市のコンクールで銀賞。そんなことになってるって知らなかったから、いきなり表彰されて、すごくうれしかった(笑)。そのときに「自分は絵が好きなんだな」ってすごく意識した。
■川勝 へえー。僕、小学校のときに描いてた絵は、いくら塗っても真っ黒になっちゃってた。
──真っ黒?
■川勝 いつも水彩絵の具が混ざって汚い色になってましたね。ちゃんと絵が描けるようになったのは、中一の授業で油絵描かされて、そこで油絵覚えてからです。そのころシュルレアリスムやアメリカ抽象表現主義を知って、抽象的な絵を描いてました。具象画は絵が下手すぎて描けなかったです。
──でも、そこからまた漫画という具象に戻っていく。
■川勝 そりゃ具象のほうが描きたいですもん(笑)。俺だって萌絵みたいなの描きたかったのに、描くと福笑いになっちゃって。
■斎藤 でも、俺も褒められただけで、うまくはないとはずっと思ってるから。
──川勝さんだってこれからも描き続けるでしょう?
■川勝 描きますよ。
■斎藤 若いからうらやましいよ。体力がぜんぜん違うもん。
■川勝 いや、僕はもともと体弱いから。すぐ熱が出るし。
──作品はどれくらいのペースで描いてるんですか?
■川勝 すっごいムラがあります。描かないときはぜんぜん描かないし、描けるときはもう天才になったんじゃないかと思うくらい描きます。でも、すぐにその才能はなくなってしまいますが(笑)。新作は次に出す『蝸牛』という同人誌に載せる中編漫画になったらいいなと思ってます。結局、僕は「漫画を描く」というより「本を作る」というモチベーションなんですよ。
■斎藤 俺は何のモチベーションもない(笑)
──でも、「こうやって自分の作品が知らない誰かに読まれている、それはなぜだ?」みたいなことは考えるでしょ?
■斎藤 そうですね。本当に自分が読みたいのを描いただけですからね。
──漫画家になりたくて、漫画家を目指してずっと描いてきた絵とか漫画とかってあるじゃないですか。ふたりとも、そういうのからいちばん自由とは感じます。
■斎藤 川勝くんは本当にふところが深いというか。俺が嫌ってるような漫画もちゃんと読んでるわけでしょ?
──そうですよね。生粋の漫画好きだと思うんだけど、漫画との距離感もすごくある。
■川勝 距離感はめっちゃあります。だって本当に好きかわからないから…。
──そこが不思議なんですよ。
■川勝 漫画がめっちゃ好きな人っているじゃないですか? 自分でもいつも思うんですよ、「俺は漫画が本当に好きか、あやしいなあ?」って。でも、漫画を読んでると「美が痙攣してる」みたいな瞬間があるんですよ。『河童の三平』とか、『わたしは真悟』とか、そういうヤバい体験がときどきあって、それを求めて漫画を読み続けてるようなところはあります。たいていはそんな瞬間には巡り会わない。だから、それを繰り返してる、というのはあるんですよ。
ただ、僕はプロデューサー的視点で漫画やってるって言いましたけど、「僕はあるキャラクターを演じてるだけ」みたいな物言いはクソダサいと思ってます。漫画はもっとマジで描いてます。基本的には、すごく真面目なんです。
──少なくとも『死都調布』や、去年「電話・睡眠・音楽」を「トーチweb」で読んだときのゾワゾワくる感じは、僕には“年に一冊”クラスでした。今年、この2冊に出会えて、僕はまた漫画が好きになりました。ちなみに、今回の『電話・睡眠・音楽』は、川勝さんの処女作品集『十代劇画作品集』になぞらえていえば、『二十代前半作品集』ですね。
■川勝 じつは、誰にも読めない字で『二十代劇画作品集』って総扉に書いてあるんですよ。
──本当だ! でも、まだ二十代はあと5年くらいありますよ。
■川勝 そしたら『パート2』を出します。
──『死都調布』も、いつか映画にしたいくらいですけどね。海外の監督でもいいかもしれない。
■斎藤 キム・ギドクとか。
■川勝 カウリスマキ!
■斎藤 黒沢清。
■川勝 いいですね。
■斎藤 黒沢清がいちばんいいです。
──じゃあ、黒沢清さんに映画化のラブコールを送っておきましょう。『死都調布 南米紀行』も楽しみです。
■斎藤 おもしろくはなると思います。
──みなさんそうだと思うんですけど、とにかく、斎藤さんのも川勝さんのも「次の一手」にめちゃめちゃ期待してます!
◆お知らせ◆
-
「この作品にふさわしい言葉をようやく思い出しました。ヌーヴェルヴァーグ。それです」(小西康陽)
ひとり暮らしの女性の日常と東京の夜景を通して現代の時間の流れを切り取った表題作ほか、龍になろうと修行した男がウナギになって食われる「龍神抄」、赤塚不二夫の満州引き上げ体験を絵物語にした「赤塚藤雄の頃」、藤枝静男や梅崎春生の短編を漫画化した「妻の遺骨」「輪唱」など、新時代のリアリズムを切り拓く1+13編を収録。
