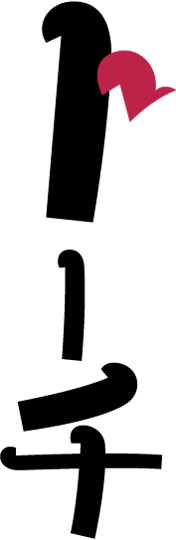今からちょうど3年前、2018年の梅雨どきだったと思う。編集部の電話が鳴ったので出ると、
「あのですね、ちょっと、漫画をですね、描いてましてですね」
といきなり言う。関西弁。若い男性。こんにちはも初めましてもなく、また、名乗りもせずに話し始めたわりに「あの、あれ、何でしたっけ? あれですわ」用件をなかなか言わない。
「原稿持ち込みをご希望ですか?」
「いえ、というか、ああ、そうですね、そんなようなものですね」
初めての持ち込みで緊張しているというよりは、人に聞かれてはまずい話でもしているかのような落ち着きなさが電話口から伝わってきた。そのくせ、なんかふてぶてしい。新人漫画家からすれば権威的に見える商業出版に対する一方的な苛立ちと媚びが胸の内でせめぎ合っていて、その決着がつかぬうちになかばやけくそで電話をかけはしたけどどないやねん、わけわからん、という風で、面識も無く声を聞いたことすらないのに、これはもしかして大山海ではないか、と私は思った。
私はこの前年に、川勝徳重の論考「一九七〇年前後の『ガロ』の技法 畳の目から『私漫画』を考える」(セミ書房刊「架空」16号収録)で大山海の名前を知り、その後、デビュー作である『頭部』と処女単行本『東京市松物語』(青林工藝舎)とを読んでいた。いずれの作品も青春時代の屈託、感傷、情熱、あらゆる権威に対する怒り、みたいなものが常人離れして物凄く、話の筋も一つの物語としてしっかりしていて、腕っぷしの強い作家だなあと感心していた。『東京市松物語』は、漫画作品であるにも関わらず表紙に絵を一切使わず作者本人の写真を採用する、井上則人による大胆な装丁で、帯には峯田和伸とみうらじゅんの名前があり、巻末には町田康の解説「小さき者達の大きな叫び」が収録されていた。奥付の写真撮影の項目には、ユキユキロと羽生生純もクレジットされており、20歳の若者のセンセーショナルな登場に衝撃を受けたのだが、日常生活というのは恐ろしいもので、家のことや日々の仕事に追われるうちに彼のことは普通に忘れていった。
そんなこんなで、この変な電話を受けてピンとくるものがあり、私の所属部署と名前を告げ、来社の日取りを決め、最後に名前を尋ねたところ、はたして大山海なのだった。
それから約半年の準備期間を経て、2018年12月から『奈良へ』の連載は始まるのだが、ほぼ同時に連載が始まった作品に不吉霊二の『あばよ 〜ベイビーイッツユー〜』がある。これは足立守正の書評(クイックジャパン149号)から少し長めに引用すると、「抑制も、屈託も、直線も、筆記具へのこだわりもない、持ち前の自由な作風には、時間の感覚もない。最先端なのに、母親の学生時代のノートから発見されたようなノスタルジーもある」「いつしか、読者はラメ入りのマドラーでくるくるかき混ぜられ、苦くて甘くてふざけた色のカクテルの渦の中へ。」という作品である。鮮烈で、良い意味で野蛮で、チャーミングで……本稿は『奈良へ』の編集後記ではあるが、この場を借りて改めて強く推すものである。
当時、不吉霊二は早稲田大学、大山海は日大芸術学部に通う学生だった。二人とも21歳。同い年の二人の連載が同時期に、しかも同じ雑誌で始まることに、39歳だった私は「奇縁であることだよ…」としみじみ感じ入ったものだが、その後の二人の様子は全く違っていてすごかった。
不吉霊二は、それから1年で全11話を見事に描きあげ、2020年1月末に宝石箱のような単行本を上梓、同年3月に大学を卒業した。一方の大山海はグズグズしていた。大学を中退し故郷の奈良に居を移していた。その時点で連載はまだ折り返し点にも至っていなかったと思う。彼が東京にいた頃は時々高円寺で一緒に酒を飲んだりできたが、奈良に転居してからはそうもいかず、私は心配だった。たまに更新されるブログを覗くとデッサンの練習を愚直に続け、読書をし、風景を撮り、孤独にのたうちまわりながら人間について、芸術について考え続けているようだった。記事から伝わってくるその日々はストイックで泥くさく、『あばよ〜』の書評から言葉を借りれば「抑制と屈託をごりごりに発酵させたどぶろくの渦に身を投じ、なんか謎に溺れているよう」だった。溺死しそうなので手を差しのべたくても、「ありがとうございます、もうちょっとじたばたしてみます、すんません」という答えが返ってくる。
そんな風にして2年以上をかけて完成したのが『奈良へ』であり、そうまでして彼はいったい何を頑張ったのか。
以下は連載を始める前に確認し合った創作上の取り決めのようなものである。
①オムニバス形式の連作にする
②各話、奈良の名所を舞台とする
③モブをないがしろにしない
④全話を通して読んだ人が「一つの物語を読んだ」と感じられる結末にする。
連載が進むにつれ私が目を見張ったのは③についてだ。①〜④は互いに複雑に影響し合っているのであまり単純化するのは良くないが、それら複雑な影響関係を生み出しているというか呼び込んでいるのは、たぶん絶対③である。
漫画において「モブをないがしろにしない」とはどういうことか。これは言い換えればモブを丁寧に描くということで、線を丁寧に引くという手技的な面と、心を込めて描くという心理的な面がある。では「モブ」とは何か。モブとは大衆、群衆、群れを意味する言葉であるが、結論から言うと、主人公も脇役も動物も風景も全部モブみたいなもので、だから、ないがしろにできるものは一つもない、という作者の見立てないし発見が本作をここまでの傑作にしたのではないかと私は考えている。
主人公以外の人間はモブやな。ほならないがしろにしたらあかんな。この作品では主人公は毎回変わるから、主人公もある意味モブみたいなもんやな。これもないがしろにできんな。鹿はどや? モブやな。一生懸命描いたらなあかんな。寺は背景やからモブみたいなもんやな。ないがしろにでけへんな。ドリームランド。廃墟やな。寺以上にモブやな。丁寧に描かなあかんな。そうすっとこの世のものは全部モブやな。この世のものを全部丁寧に描かなあかんいうことは、あの世は雑でええんか。雑でええとすれば、あの世はモブっちゅうことやな。ないがしろにでけへんな……なんやこれ全部やんけ。森羅万象やんけ。どないせえっちゅうんじゃ。
私の素人関西弁はお目こぼし頂くとして、もちろん作者は、こんなふうに最初に③のルールありきの順序立てた考えに基づいて作品を組み上げていったわけでは多分ない。右に綴った理路は、ばかがつくほど正直で、危なっかしいほど思いやり深い作者の人柄から逆算した後付けの妄想に過ぎないのだが、この、疎外され誰にも顧みられぬ存在をなぜか絶対に見落とすことができない作者の本性というか、見落としてなるものかという意地というか、強烈な衝動というか、そういうものに本作は貫かれていて、その視線の鋭さ、深さ、広さには鬼気迫るものがあるということが言いたかった。
皆さんはウィキペディアの奈良ドリームランドの項目を読んだことがあるだろうか。ものすごく切ない。奈良ドリームランドは、開園前から「ディズニーランドの日本版」を自称し、積極的に広告展開をしていたが、園の写真を見たウォルト・ディズニーが激怒。「もう二度と日本人なんかと仕事するか! あいつらは絶対に信用しない!」と怒鳴り散らしたらしい、ということが書かれている。「奈良ドリームランド側は『ディズニーランド』を名乗るためにディズニー側と交渉に臨んだが、無論ディズニー側には、そのような考えは毛頭なく〜」の箇所だけ読んでも、私は涙が出てくる。生前のウォルト・ディズニーを激怒させ、国内外から疎まれつつ閉園。長いあいだ放置され、やがてバス停の名前からも外されて時間とともに忘却の彼方に追いやられていく……大山海がそういう場所をクライマックスの舞台に選び、大変な労力をかけて描き切ったことの意義は大きい。
******
今回、解説を町田康氏に依頼した。作者には言わずに私が勝手に依頼した。大山作品では『東京市松物語』に続き二度目の解説になるので、引き受けてもらえるか不安だったが、『奈良へ』の解説をお願いするとすればどう考えても氏しかおらず、思い切ってメールを送った。数日後、引き受けてくださる旨、手短な返信があり、その末尾に一言「『奈良へ』拝読しました。とても良いと思いました」と添えられていた。
装丁の川名潤氏へは、5月の連休をはさみ、〆切りまで時間の無い中での依頼となった。にも関わらず「作品読みました。謎の使命感に駆られてお引き受けすることにしました」というお電話を頂いた。お二人にこの場を借りて御礼を申し上げます。
連載中、一度だけ大山くんを訪ねて奈良へ行ったことがある。京都へは出張や旅行で何度か行ったことがあるが、奈良は初めてだった。大山くんが奈良公園を案内してくれた。若草山を歩いた。ゆるやかな丘陵の向こうに広がる夏空の奥行きに果てがないことを感じた時、自分の足元が古代と地続きであることを、一瞬だが確かに感じた。それはほっとするような、そんなはずはないのに自分一人が取り残されて心細いような、不思議な感覚だった。また来たいと思った。
(編集部・中川)