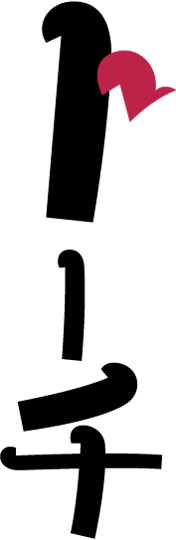こんにちは、中川です。
『愛人 ラマン』フランス語版の巻末に私の文章が収録されています。高浜さんが序文を書き、私が跋文を書きました。
日本版には序文はなく高浜さんの文章が「あとがき」として収録されています。ちなみにイタリア語版は序文が高浜さん、跋文は作家のフランチェスカ・スコッティ氏です。
エージェントのカンタンさんを通して文章の依頼があった時、私は一瞬で天狗になりました。俺もワールドワイドだな。北海道の田舎から東京に出てきて20年、額に汗して働いてきたけれども俺の器は今や東京でも収まらんちゅうこっちゃ、と。
ところが、いざ書き始めてみてびっくりしました。何を書けばいいかひとつもわからない。フランス版にフランス語で収録されるものなので当然フランスの読者に向けて書こうと思いました。しかし彼らにとって私などマジで誰だこいつですから、野暮、場違い、ださ、うざ……まだ書き始めてすらいないのにフランスの読者たちの声が聞こえてくるようでした。一方で、日本代表ヅラしてんじゃねえぞシャバ僧が……日本の読者や評論家の声も同じくらいの強度で聞こえてきました。
ビビってビビってビビり倒し「高浜さん、どうしましょう、手が、頭が、ピクリとも、動きません……」電話で泣きつきました。
「わかるよ。フランスの人たちが自分に何を求めているかわからないから書けないんだよ。でもそれを知ることはできないから、そういう時は自分の知ってることを書くしかないんだよ」
高浜さんはそんなようなことを言ってくださいました。相手がフランス人だろうと日本人だろうと、自分が書いたものを他人に読んでもらうというのは恐ろしいことだと知りました。他人が何を求めているかを読み取る知性と感性が問われるし、それに何より、姿も見えず何を考えているかもわからない他人を前に自分を信じて賭けてみる勇気が求められるのだなと。こういう戦い(私には戦いに思えました)を常に続けてるわけですから、作家というのはすごいなと改めて思いました。そういう人たちの背中を押せる人になりたいなと思いました。
日々の現場で感じていること、高浜さんについて、そして『愛人 ラマン』について思っていることを正直に絞り出したつもりです。至らぬところ多々あるかと思いますが、よろしければお読みください。
学びの機会をくださった高浜さん、私の怪しい日本語をフランス語に訳してくれたカンタンさん、収録してくれたル・ド・セーブル社に感謝します。あと「あの文章よかったですよ。公開しないのはもったいないですよ」と言ってくださった往来堂の三木さんにも。
ーーーーーー
『愛人 ラマン』フランス語版あとがき
編集者として高浜寛とはじめて仕事をしたのは2014年に雑誌連載がスタートした『蝶のみちゆき』である。「コミック乱」という時代劇画誌の編集部への配属を機に、日本の幕末を舞台にした作品を彼女に依頼した。以来、同作の単行本化、『SAD GIRL』の邦訳、『ニュクスの角灯』(全6巻)、そして本作『ラマン』に至る日本での仕事を共にしてきた。
高浜寛の経歴は日本の漫画家の中でも特殊なものだ。他の多くの漫画家に比べて海外、とりわけフランスでの活躍が群を抜いており、その評価もまた国内よりもフランスが先行してきた。2001年のデビューからもうすぐ20年になるが、国内の主要な漫画賞の候補に彼女の名前が上がり始めたのは、ようやくここ数年のことだ。2016年・2017年の手塚治虫文化賞で『蝶のみちゆき』と『SADGiRL』が最終候補に選ばれ、2018年の文化庁メディア芸術祭で『ニュクスの角灯』が優秀賞を受賞した。しかし、それまでにデビュー作を含むほぼ全ての作品が仏語訳されてきたことや、カルティエのブックレットへの寄稿、アングレームをはじめとする国際漫画祭への招待・参加歴などを鑑みると、国内での評価は決して完璧なものではなかった。言うまでもないことだが、これは彼女の作品が選考に耐える水準に達していなかったからでは決してない。昨年、文化庁メディア芸術祭の贈賞式後のパーティーである審査委員がこう言った。「この作家の存在に長いこと気づけないでいた自分を情けなく思う。今回、ようやく然るべき賞を贈ることができてホッとしている」。作家への最大限の祝意とエールが込められており強く印象に残っている。
高浜作品は、商業的な側面から言えば、『NARUTO』や『ONE PIECE』のような数千万~数億部クラスのヒット作ではないものの、丁寧で奥ゆかしい作者の手つきが読者の心を確実に掴み、少しずつ、しかし着実にファンを獲得してきた。このような、静かに輝きを放つ才能が国内の賞に「発見」されるまでにかくも長い年月を要したことは、多様性・質・量における日本の漫画の圧倒的な豊かさと、それらと表裏をなす市場の苛烈さを考えれば無理からぬことかもしれない。日本では現在、年間で1万2000点を超える新刊漫画が刊行されている。毎月約1000タイトル以上が書店に送り込まれている計算だ。紙の本だけでこの数だから、ネット書店、電子書籍、サブスクリプション、さらにわずか3日間で70万人を動員するコミケや1度の開催で約5000サークルが出展するコミティアなどで販売される自費出版も含めると、いったい私たちの国では年間でどれだけの漫画が売買されているのだろう……と気が遠くなる。
だからといって高浜寛が日本で全く無名だったかというと全然そんなことはなく、日本で20年間、プロの漫画家であり続けている。これは大変なことだ。何をもって「プロの漫画家」とするかは国や時代、定義する人の立場によって様々だと思うが、日本の漫画編集の現場で働いている私の素朴なイメージとしては、商業媒体での定期連載を持ち1~2年に1冊以上の新刊をコンスタントに刊行している漫画家、というものだ。先に述べたように日本の漫画市場は苛烈なものだから、プロとして漫画を描き続けることは簡単なことではない。胸の痛いことだが、素晴らしい独創性を持ちながら商業として上手くいかないことで創作の道を諦めざるをえなくなった漫画家は沢山いるし、マーケティングを重視する(あるいは出版社によって重視させられる)あまり、独創性を失い創作への情熱を持続できなくなってしまう漫画家も少なくなからず見てきた。高浜寛はそのどちらでもない。市場から逃げず、かつ翻弄されることなく自らの表現を鍛え研ぎ澄ませていくことのできる数少ない漫画家の一人である。
プロフェッショナルという言葉は芸術家にとっては必ずしも褒め言葉ではないのかもしれないが、彼女は間違いなくプロフェッショナルであり、そして芸術家である。洗練された描線、先鋭的な陰影表現、深い人間愛と透徹したリアリズムがもたらす叙情を表現できる漫画家を私は彼女の他に知らない。彼女がどのような芸術家であるかは私の拙い言葉で説明するよりも、日仏両国の巨匠の言葉を引くのが早い。以下はペータース&スクイテンと谷口ジローが2015年に刊行された『蝶のみちゆき』に寄せたものだ。ここに改めて記しておく。
「本作『蝶のみちゆき』の少なからぬ魅力は、ヒロイン・几帳がたたえる穏やかな悲しみにあり、読む者を幕末・明治の遊女の世界へと導く官能と情緒にある。私たちは初期作品からずっと高浜寛の繊細な仕事に注目してきたが、彼女はこの作品により世界的コミック作家の最高峰へ至る新境地を切り拓いたようだ。」(ブノワ・ペータース/フランソワ・スクイテン)
「今、最も読まれるべき漫画がここにある。知っているようで知らない時代、美しき遊女のお話。なんとも気負いのない絵と語りのうまさが際立つ。心が揺れる―高浜寛の物語表現は描く度に高まってゆく。」(谷口ジロー)
ペータース&スクイテンは「最高峰へ至る新境地を切り拓いた」という言葉で、また谷口ジローは「描く度に高まっていく」という言葉で、高浜寛がこの先さらに優れた作家になるだろうことを示唆しているのが興味深い。それは彼女の最高傑作は常にこれから描かれる最新作であることを意味してもいる。事実『蝶のみちゆき』の次に描かれた『ニュクスの角灯』で彼女は国内の評価を確たるものにし、更に最新作である本作でフランス文学の不朽の名作を世界で初めて漫画化することになった。
私が『ラマン』の存在を初めて知ったのは映画の宣伝だった。邦題は『ラマン/愛人』となっていた。当時まだ12〜13歳だった私は「愛人」という言葉の持つスキャンダラスなイメージばかりを受け取り、映画にも原作にも触れないうちから自分とは関係のない世界のものだと思い込んでしまっていた。フローベール、カミュ、サルトル、セリーヌ、ベケットなどフランスの近代文学に親しむようになったのはその後10年以上が経ち出版社に勤めるようになってからで、デュラスの『ラマン』を初めて読んだのもその頃だ。読んで驚いた。長年、通俗的な恋愛劇だとばかり思い込んでいたものが、実は切実な愛の物語であること、そして極めて前衛的な作品であることを知った。以来、本棚にデュラスの作品が2冊3冊と増えていくことになるが、偉大な芸術作品のほとんどがそうであるように『ラマン』もまた、私たちが抱える愛についての、また時間についての困難にわかりやすくケリをつけてくれるものではないけれど、それらについて考えを深めたり豊かに感じたりするためのたしかな足場となる頼もしい存在であり続けてくれている。
今回、高浜寛という優れた漫画家を通してこの作品に新たに出会い直せることを私は本当に幸せに思う。日本の編集者として、また、いち読者としてフランスの皆さんと共に本書を手にできることをとても嬉しく思っている。