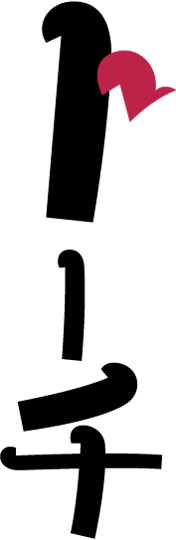高浜寛さんの『ニュクスの角灯』が第50話をもって最終回を迎えました。掲載誌の「コミック乱」2019年8月号は現在、書店やコンビニなどで絶賛発売中なのでぜひお手にとってみてください。単行本で読む派の方は、最終話収録の第6巻が8月27日に発売されますので楽しみにお待ちください。
同作は1944年の熊本の空襲の場面から始まり、1878~79年の長崎とパリでの出来事が描かれ、最終話で再び1945年に戻りラストシーンに至ります。私がこの結末を知ったのは4年半前になります。連載開始前に高浜さんが送ってくれた全体の構成案に今回の最終話の構想がすでに書かれていました。同作の雰囲気を基礎づけるベル・エポックの華やかさと対照的な、結末の重厚さというか、現代を生きる私たちへ鋭く問いかける内容にとても驚きました。
連載が始まる前は全18話、単行本で全2巻の予定でした。ただ、人気が出てそれ以上に長くなるケースもあらかじめ見越し、全30話くらいの構成も事前に用意していただけますかと図々しいお願いをしました。高浜さんは18話を30話に薄めて引き延ばすのではなく、新しいエピソードを盛り込む形で構成した上で連載は始まりました。
第1話の原稿を初めて見せてもらった時、高浜さんは高円寺の商店街にあるケバブ屋の2階に投宿していました。通りに面した扉を開け、人ひとりがやっと通れる急な階段をギシギシ登った先に共用の台所があり、そこで拝見しました。冒頭、美世が「蛮」の門を叩き、百年がパリ万博から様々な舶来品を仕入れて帰ってきたシーンでした。横でコーヒーを淹れていた外国人のバックパッカーが原稿を見たそうにしていたので見せてあげると、にっこり笑って「クール」と言いました。
連載が始まり単行本が出ると度々重版がかかり、新聞・雑誌・テレビなどでも紹介され、国内外の漫画賞へのノミネートと受賞、海外版の出版などなど予想以上の反響があった一方、熊本地震や他社あるいは海外出版社からのオファーによる月産ページ数の急増など、大変なことが次々と起きる中、すみませんやっぱり3巻分……いや4巻分……いや……とお願いを重ねることになりました。高浜さんはその度に快く応えてくださり、それだったらこれが描きたかった、新しい資料を見つけたから盛り込みたいと、ほとんど無尽蔵にアイディアを出してくださり、連載に対し前向きに、また自作への愛情を失わずに全50話を描き切ってくださいました。連載中のことについては「トー通」第6号と第10号で少し書いたことがありますので、お時間のある方は覗いてみてください。
全6巻、既刊を既読の方も未読の方もぜひこれを機に2度3度と通読していただきたいです。1度目では測りかねた細部の描き込みやふとした台詞にハッとすることがあると思います。作品に身を任せて、ゆったりした気持ちでお楽しみください。
最終話掲載誌の発売から1週間が過ぎましたが、この間、読者の方から編集部に何本も電話がかかってきました。作品の感想がSNSなどに書き込まれることは少なくありませんが、電話でこれだけの感想を頂くのは私は初めてです。作品の感想とともに完結を惜しむ声と著者への労いのメッセージをいただきました。私は学生の時にデパートのクレーム対応のアルバイトをしていたことがあり、いまだに机の電話が鳴るとビクッと身構えてしまうのですが、これまでサイレント・リーダーとして無言で楽しんでくれていた方々の、心のこもった言葉を頂戴するたびにその怯えが溶けていくような気がします。本当はぜんぶ録音したいくらいですが録音してません。メモを取っているので後日書面にまとめて著者に送ろうと思います。
興味深かったのは1945年の、もっと言えば1945年の長崎の遠景が描かれた最終話に対し「希望に満ちた結末だった」という方と「悲しい結末だった」という方が両方いらしたことです。電話口でお話を伺いながらどちらもまったくその通りだと思いました。どちらの解釈が正しいとか作者の意図はどうだとかいう話は意味がないですし、そもそも私にジャッジできるはずもないですが、私が確実に言えることが一つだけあって、それはこの結末というか作品には高浜さんの透徹した現実観が強く反映されているということです。
現実をどのようなものとして考えるかは作家によって様々ですが重要で、高浜さんの作品に関して言えば、現実というのはままならないものだ、という見立てが全ての作品に一貫しているように思います。前提とされるままならなさはいくつかのわかりやすい言葉で表すことができます。人は必ず誰かを愛してしまう、人は間違う、人は必ず老いる、人は必ず死ぬ、です。2001年に「ガロ」でデビューして以来、処女作の『イエローバックス』から『ニュクスの角灯』に至る18年間の作家活動の中で、手厳しい現実はひとまず置いといて……という姿勢で描かれた作品は1つもないのではないか。高浜さんの作品には「どう生きるか」という問いの答えを「なぜ自死せずにいるか」からの逆算で求めるような感じが常に漂っているように思います。ハードな現実の中で、なけなしのユーモアを杖にして、やはりなけなしの希望を大事に拾い集めていくような……
華やかでロマンチックな雰囲気をまとっている『ニュクスの角灯』も例外ではなく、同作は主人公・美世の成長物語である一方、厳しい現実を生きる大人たちの成長物語としても読むことができます。大人たちの成長というのはちょっと変ですね。大人たちの成熟というべきでしょうか。ジュディットとの空白の時間を悔やむ百年、詐欺に遭い莫大な資産を失った大浦慶、家族の生活を一身に背負う青貝職人の叔父、誰にも心を開けない黒川などなど、いずれもわけありな大人たちです。彼らはそれぞれの苦しみや迷いを解決できぬまま、働き、愛し、食べ、眠る。完璧な大人が一人も出てこない。彼らは自分たちが抱える困難を饒舌に語ることはせず、静かに耐えている。一方で同作は高浜さんのこれまでの作品の中で登場人物たちが最もよく笑う作品でもあり、ゲラゲラゲラとかブッと吹き出す音など能天気な描き文字がよく出てきます。それらは楽しさや可笑しさの表現であると同時に、彼らの「静かな忍耐」を読み手に思い出させる装置としても機能しているように思います。
少年少女は内的にも社会的にも「大人にならなければならない(さもなくば生きていけない)」というメッセージから逃れられないものですが、美世の成長が、ある立派な人物の決定的な薫陶ではなく“複数の”大人たちの静かな忍耐に背中を押される形でもたらされるのは、この作品の持つリアリティの一つだと私は思います。
『ニュクスの角灯』は高浜さんにとって様々な意味で画期的な作品です。初の長編であること、今までの作品では主線を鉛筆で描いていたのを付けペンに持ち替えたこと(後に鉛筆に戻す)、コマ外がスミベタではなく余白になったことなど、誰もがわかる形で劇的な変化が見て取れます。鉛筆による主線やコマ外のスミベタは高浜さんの作品を特徴づけてきた手法の一つでしたが、今作での変化は、前作『蝶のみちゆき』で極まった写実的で先鋭的な陰影表現から一度離れたということでもあります。高浜さんと長い親交のある山田参助さんが『ニュクスの角灯』の第1話を読んで「あの高浜寛がアホ毛を描いた!」と驚いていたことをよく覚えています。これは編集側からの要請ではなく高浜さんの自主的な取り組みです。『蝶のみちゆき』が商業的にも一定の成功を収めていたことから、私はむしろ今までの手法を踏襲し手堅く取り組むのがよいだろうと思っており、著者もきっと同じ考えだろうと思っていたのですが違いました。新しいことに取り組みたい、変わりたい、今よりも良いものを描けるようになりたいという欲求は私が思う以上に強かった。どうなるかわからないけど賭けてみる、そして賭けに負けないというのは作家としての足腰の強さがないとできないことだと思います。一緒に仕事をするようになって5年以上が経ちますが、タフな人だなあといつも思います。『ニュクスの角灯』第48話でポーリーヌの台詞として引用されているニーバーの祈りを思います。熊本地震に関するインタビューにもあるように、高浜さんが深刻なアルコール依存に苦しんでいた頃に更生プログラムの中で出会い、今でも大切にしている言葉だそうです。
神様私にお与えください
変えられないものを受け入れる落ち着きを
変えられるものは変えていく勇気を
そして二つのものを見分ける賢さを
高浜さん、4年間本当にお疲れ様でした。連載中は色んなことがありました。大きな震災がありました。猫が増えました。月刊連載と週刊連載の同時進行がありました。谷口ジロー先生との再会が叶わず残念でした。カンタンさんとパリに連れていってもらいました。昨年のメ芸の受賞は涙が出るほど嬉しかったです。僕自身、この連載から沢山のことを学び励まされる日々でした。また、全国の書店員の方々。本当は全ての方々に直接お会いして固い握手を交わして感謝を伝えたいところですができませんので、この場を借りて御礼を申し上げます。みなさんのご協力なしに同作はここまで多くの方々に届くことはなかったと思います。みなさんの心のこもった応援がどれだけ著者と版元を勇気づけたか。
高浜さん、地震の時はパルクールの練習で鉄棒の上を歩いていたとのことですが、先日お電話した際には古武術の訓練中に腰を痛めてしまったとのことでした。巨大な鉄球を回していたとか。色んな意味で心配です。くれぐれもお大事になさってください。『ラマン』そして次回作が待っています。
(編集部・中川)