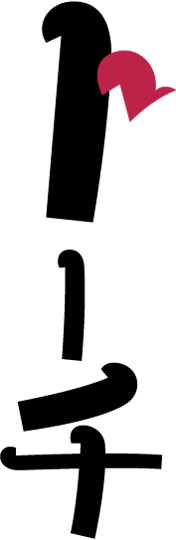世界は他者で満ちている。
「私と異なる」全ての者を他者とするなら、世界人口78億人のうちの何人が他者で占められているかは言うだけ野暮というものだ。動物や自然も何もかも他者だから、もう全部他者だ。
現代人の恨みつらみ妬み悲しみ怒り不安恥辱。生老病死の一角をなす生の苦しみの大半は人間関係のままならなさがもたらすものだ。しょせん人間関係の問題なのだから苦しむに及ばないと言いたいわけでは全然ない。人間関係というのは私たちにとって生死に関わる深刻なものだということだ。なぜかはわからないが私たちはそういうふうになっている。見ず知らずの他人はもとより、血を分けた家族も、一蓮托生の親友も、永遠を誓い合った恋人も、そしてその気になれば自分自身でさえも他者として数えることができてしまう。私と全く同じように感じ、私と全く同じように考え、私と全く同じように行動する人間は世界に一人もいない。足を踏んでいる者に踏まれている者の痛みはわからない。誰も私を生きることはできない。誰も私の死を死ねない。死後も共にあることを誓い心中してみたところでどうにもならない。落語の「品川心中」にもあるように浮世の誓いというものは笑ってしまうほど頼りないものだ。他者が他者であるがゆえの生きづらさは、つきつめれば「あなたはなぜ私ではないのだろう」だ。もし私以外の人々がことごとく私だったら私たちはこんなに苦しまなくてよかったはずなのに……私たちはばかが付くほど孤独である。
しかし人間は他者と断絶されているからこそ互いを慈しみ、思いやり、愛し合うことができる。万物が完璧に融和し何もかもがぜんぶ私になってしまったら、苦しみも消える代わりに喜びも愛も生まれぬ。だから他者の存在は救いであり喜びである……という優しげなことが言いたいわけでもない。いや、私たちが他者に苦しみ他者に救われる存在であることは事実だが、その前に、はたして私たちはこの「あらゆるものが他者である」という事実を正しく肝に銘じることができているか? ということだ。日々の暮らしの中で自他の間に横たわる絶望的に深く長い亀裂から目を逸らさず「あ、どうも、他者の方ですね。よろしくお願いします」なり「よう久しぶり! 相変わらず他者だな」なり「この他者といると心が安らぐな。この他者と添いとげたいな」なり、そういう心構えを持ち続けているか? ということだ。私は全然持ち続けていない。当たり前だ。人と見るやいちいち「他者であることだよ」などとその他者性を噛みしめていては日常生活に支障が出る。
だが常に意識はせずとも忘れてはならない。私たちはわりと人との共通点とか共通の話題みたいのを探しがちだけれど、大事なのは相手と自分のどこが似ているかではなく、油断するとすぐに相手とまじり合い同化したがる自分の欲望の有り様を知ることだ。これは何も相手が人間の場合に限らない。海や山や動物や芸術や学問や、何かを追い求め、ものにしようとすることは同化への欲望である。他者に苦しむくせに他者と同化したがるようにできている。矛盾している。苦しいのは当たり前だ。この矛盾をどう生きるか。二択である。
(1)自他の断絶はいつかなくなるものと信じ、間に横たわる漆黒の谷には目を瞑る。谷を越えられるか転げ落ちるかは運を天に任せ、他者とまじわろうと試みる。
(2)自他の断絶は絶対になくならないものと自覚し、間に横たわる漆黒の谷を見極める。この谷は決して越えられぬことを知りながら他者とまじわろうと試みる。
意志強ナツ子の作品は、(1)を選び谷から転げ落ちそうになっている者には一度しっかり落ちて大怪我をすることで谷の深さ・幅・形状を知ることを推奨し、(2)でありたいと願う者には目を見開き谷を覆い隠す霧を振り払う勇気を与えるものである。ソーシャルディスタンスの向こう側からわかりみを投げてよこすようなイージーな慰めと彼女の作品と、人類への贈り物としてどちらが貴重なものであるかは論をまたない。
『アマゾネス・キス』は意志強ナツ子初の連載長編である。全17話、全3巻、総ページ数772ページ。連載期間は2017年10月〜2020年8月。本作の話数表記は「Lesson.〜」である。当然Lesson.1から始まるわけだが、見えないがLesson.0があると私は思う。そこには「自分と他者の間に絶望的な断絶があることは皆さんもうご存知ですね。本当につらいですよね。さて……」という前置きが書かれている。意志強ナツ子はずっと他者について描いてきた。「女神」「KEBAB」「まこちゃん式画塾」「コリコリ屋さん」「魔術師A」「呪術師A」。デビュー単行本『魔術師A』収録の短編全てに、主人公が他者から否応なく切り離される瞬間、あるいは自分を他者から切り離す瞬間が描かれている。「私たちって本当に他者なんだ! 意外!」という感じだろうか。「意外!」の部分は作品によって「最悪!」だったり「不思議!」だったり「だと思った!」だったり「最高!」だったりするが、思いを寄せる人との同化に失敗したり自ら拒絶したりして他者が完成することは各編に共通しており、『魔術師A』の到達点が『アマゾネス・キス』の出発点になっている。
彼女は「アマゾネス・キス読本」に寄せた「意志強ナツ子からみなさんへ」の中で、本作についてこう書いている。
見切り発車のように強引にスタートしたような漫画でした。
おおまかな方向性は決まっているものの、どう展開していくかが決まっていないため、その時々の怒りや悩み、発見などを盛り込みながら、1話ずつ考えていきました。
彼女は本当に1話ずつ考えた。連載を始める前に用意した見取り図に沿って予定をこなしていく描き方では連載を始める前の自分を超えることはできない。1話描く度に、描く前には想像もつかなかった自分に変化すること以外に創作の快楽はないとでもいうように、彼女は1話1話すべてを出しきってから次を考えるやり方を当然のように選んだ。苦しいやり方だ。全3巻を無事に刊行できて私は心の底からほっとしている。「『アマゾネス・キス』、何がエビデンスか」という記事で「意志強さんはいつもいきなり苦悩している」と書いたように、創作に対する彼女のストイシズムは大変なものだ。彼女は作話の間に髪を抜く。沈思黙考、一本一本抜いていく。昨年の夏、Lesson.11のネームが難航した時、彼女は「行き詰まってます。飲みませんか」と言って高円寺にやってきた。あの時彼女はハゲていた。心配だった。彼女が病んでいるから心配だったのではではない。逆で、彼女がいつもと変わらず正気だったからだ。追い詰められ逆上した漫画家が髪をひきむしるなら止めようもあるし、かける言葉も心得ているつもりだが、正気の人が正気のまま一本一本髪を抜いていく姿を前にすると、何というか、緊張するのである。神へ供物を捧げる儀式に立ち会っているかのような……励ますことも止めることもできず、ただ息をのんで成り行きを見守るしかない。次に会った時にハゲが治っていたのも不思議だった。私が「髪、戻りましたね」と言うと彼女は「ええ。戻りましたね」と言った。
漫画を描くというのは神秘的な行いだ。紙とインクだけで人間や景色や出来事を創出して見せようとする。神でもない我々になぜこんなことが可能なのだろう。意志強ナツ子の創作に対するストイックさを見ていると、創作というものが神の領分を自らかすめとりにいくような不遜で危険な行為であるようにも思えてくる。『アマゾネス・キス』全編を覆う不穏さは超感覚知覚とか人間力とか占いとか体外離脱とかナンバーズ予想とか、カルトっぽく、いわゆるスピリチュアルな題材によるものではない。問題は題材がこんなにもカルトっぽく、いわゆるスピリチュアルな感じなのに、神に救いを求める人物が作中に一人もいないことにある。
『アマゾネス・キス』には実は「神」という言葉が出てこない。はづき、純子、アケミ、虎徹、乃亜、ヘラクレス義雄、門抱、エルザも、神どころか何かに「救いを求める」ということをしない。誰にも救いを求めない代わりに、自分で考えて、自分で決めた、なんか、変な、オリジナルのルールに従って「高みを目指す」のである。彼らの眼中には最初から神など無いように見える。意志強ナツ子が本作で前提とする「自他の断絶」には神との断絶も含まれている。だからLesson.0にはこうも前置きされている。「自分と神の間に絶望的な断絶があることは皆さんもうご存知ですね。本当につらいですよね。さて……」。
私たちは神の機嫌を損ねるとひどい目にあったり死んだりすることを骨の髄まで叩き込まれているから、神をガン無視しつづける『アマゾネス・キス』の面々を見ていると何だか不安になる。もし私が神だったら「無視しくさって!」と怒るだろう。しかし、だからこそ彼らは気高い。私たちが他者に苦しみ他者を求める宿命を背負ってしまったのはアダムが神の言いつけを破り禁断の果実を食べてしまったからで、アダムの野郎本当にばかなことをしてくれたと腹が立つ。しかし本作を読んでいると、ちょっと待てよ、考えてみれば「ここの果実、食べるとひどいことになりまーす」と、人も動物も誰も同意していない謎ルールを考えて一方的に施行したのは神だよな……という気になってくる。相手が人だろうと神だろうと手加減せず等しく他者とし、そこから始める。この厳格なフェアネスはこの著者の人並みはずれた真面目さの現れであり、作品のリアリティを決定づけている最大の要因だと私は思う。
連載が始まる前、Lesson.1のネームの一稿目では「アマゾネス・キス」は「魔術師育成スクール」となっていた。描いた本人が一番納得していなかった。二稿目でもアマゾネス・キスは「スクール」となっていた。やはり本人は全然納得していなかった。「近くはあるんですけど、なにかが違う…」髪を抜きながら考え込むので「新興宗教のようなものですか」と尋ねると無視された。アマゾネス・キスとは一体何なのか。三稿目で「トレーニングジム」という言葉が出てきた。アマゾネス・キスを「教えを与える/与えられる」場ではなく、「自らを鍛える/鍛えてもらう」場と定めたことで作品に背骨が通ったというか視界が開けたというか、そんな感じがしたし本人も「手応えがあった」と言った。その手応えは、今後の展開に一筋の光明が見えたというものではなく、これから始まる連載に苦しみ甲斐を見出せたことの喜びでもあるように見えた。誰かから与えられた苦しみではなく自ら見出した苦しみを苦しみ、成長できることの喜び。
正しい行いをすれば救いの手が差し伸べられるわけではない。驚くべきはやはりその結末で、ばかみたいに孤独で不遜で不敬な者たちが、嘘なく全力でがんばった結果迎えた堂々たるハッピーエンドは、神の死後を生きる私たちへの大いなるプレゼントである。全3巻、まだ読んでいない方はぜひ読んで、圧倒され、感動してほしい。偉大な作品が生まれる場に立ち会えたことを私は感謝している。神にではなく意志強ナツ子に。
意志強さん、素晴らしい作品をありがとう。がんばってがんばってがんばり抜いた3年間でしたね。本当にお疲れ様でした。これからも身体に気をつけて、ますますの活躍を期待しています。
(編集部・中川)