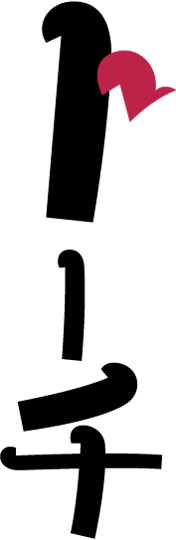わんちゃんたちについては当初、著者のあとがきとして単行本の巻末に収録するのがいいだろうと私は考えていて、川勝さんにお願いして実際に原稿を書いて頂いたのですが、本書の制作が後半にさしかかり、その完成形がだんだん見えてくると、本編の最終ページ(「ロイコクロリディウムの恐怖」)の「開かれた静寂」を残したまま本を閉じてもらうのが正解だと思うようになっていきました。著者の川勝さんと装丁の森敬太さんと相談の上、あとがきはまた別の形でみなさんにお届けしようということになりました。なのでここではひとまず、本書がどういう経緯でこの表紙になったのか、編集の立場から記しておこうと思います。
本書の表紙の写真は台湾の漢聲出版が2005年に刊行した犬のポスター集『2006大過狗年』に収録されていた【愛狗圖】という作品です。装丁の打ち合わせのため川勝さんと一緒に森さんの事務所にうかがったところ、壁にこのポスターが貼ってありました。玄関で靴を脱いで最初に目に飛び込んできたのですが、私がその時感じたのは(犬であることだよ)ということで、その気持ちはこれから始まる打ち合わせには必要ないものだと思ったので一旦忘れました。打ち合わせは、私と川勝さんがテーブルの手前に並んで座り、向こう側に森さん、そして森さんの背後にこのポスター、という位置関係で進んだため、森さんの方に目をやる度に視界の端にポスターが映り込んで、私は都度(犬であることだよ)と思い、いかん、打ち合わせに集中せねばとかぶりを振りました。
誰も犬ポスターに触れることなく打ち合わせは順調に進みました。わんちゃんたちと何度も目が合いました。するうち、今回の作品集に色濃く反映されている「動物への暴力」に対する川勝さんの不思議な関心を、彼らが見事に代弁しているように思えてきて、「表紙…に…?」という考えが首をもたげたのですが、その考えはあまりに非現実的なものに思われたので黙っていました。この時点ではまだ誰が何の目的で作成したものなのか、一体どこの誰にどういう形で許諾を取ればいいかもわからなかった上、どうやら海外のもののようでなおハードルが高い。仮に申請先がわかったところで許諾が得られるとも限らない……
判型や用紙や表紙絵のだいたいの方向性が決まってきて、森さんが別のお仕事の電話のために少し席を外した時に、川勝さんが壁のポスターを見つめたまま「あれヤバイですよね」と言いました。川勝さんもやはりずっと気になっていたようで「なんでしたっけ、あのジャケ、似てるんですけど思い出せなくて……」と言う。戻ってきた森さんに色々尋ねたところ、森さんが台北に行った時に買ってきたポスター集の中の一枚で、とても気に入って貼っているということでした。三人で「表紙にできたらすごいですね」という話をしながらも、打ち合わせを終え帰り支度をしている段階でもまだそれは楽しい空想の域を出るものではなかったように思います。
しかし(おそらく川勝さんは最初から心を決めていたのだと思いますが)、帰り道で川勝さんと話をする中でMangasickさんなら取り次いでくださるかもしれない、という具体的な話も出て、彼と別れて一人で電車に乗る頃には、これは本気で取り組む価値のあることだ、という気持ちになっていました。編集部に戻ると川勝さんから「ジャケ、インプレッションズの『伝道者』(1973)でした」

というメールがきており、このことを森さんにお知らせし、犬ポスターを表紙にすることを改めて提案しようと電話に手を伸ばしたまさにその時、森さんの方から「犬ポスターの素材使用、本気でいいなという気がしてきたので、許可取りについて真剣に検討して頂けないでしょうか?」というメールを頂いたのでした。
本が刷り上がった今となっては、表紙がこの形になったことは著者と装丁家の強い思いを受けての当然の帰結だったと言えるのですが、漢聲出版さんに使用許諾を求めるにあたっては、川勝さんが本書で何を描いているのか、なぜこのポスターが必要なのか、こちらの意図をちゃんと伝えなくてはなりません。先述したように、この犬たちは「動物への暴力」に対する川勝さんの不思議な関心を見事に代弁している、という直観が私にはあったので先方に伝えようと思いました。作品の解釈を浅学を承知で手探りで書き綴らざるを得ませんでしたが、その理路を以下で説明しようと思います。的外れなところもあると思いますが、試論としてご海容いただきたいです。
書名にある「アントロポセン」(Anthropocene)は「人新世(じんしんせい/ひとしんせい)」と訳されています。地質学の言葉で、21世紀に入ってから盛んに議論されるようになってきたそうです。現代における自然破壊、生態系の崩壊、気候変動というのはもはや「人類史上〜」とか「有史以来〜」と言った言葉では括れぬスケールのものになってしまっていて、地質学的な区分として成立する(ほど取り返しのつかない)ものだ、という実感とともに提出された言葉だと思われます。
『野豚物語』を例にとると、川勝さんは現代がこの人新世にあることを前提に「資本主義」「差別」「変革」について描いているものと私は読みました。主人公の女性は東京(と見て差し支えないと思います)で暮らす一般的な若者で、彼女の生活はスマホ・SNS・YouTubeと不可分なものとして描かれます。ここから連鎖していく形で、現代を生きる私たちは好むと好まざるに関わらずGAFAの恩恵にあずかってしまっている→資本主義の恩恵にあずかってしまっている→近代の恩恵にあずかってしまっている→西洋の植民地主義の恩恵にあずかってしまっている、といったことが前半で読み取れるようになっています。
近代というのは、植民地と宗主国、労働者と資本家、有色人種と白色人種、南半球と北半球……といった対比を持ち出すまでもなく、必ず何らかの格差の上に成り立ってきたもので、動物と人間との関係もその一つです。とても残念なことですが、事実、私は今、蟻やダンゴムシらを大量虐殺して舗装した土地で本稿を書いているのであり、近代都市で「普通に暮らす」私たちはもうそれだけで何らかの差別に加担してしまっている。動植物を好き放題に制圧してきたあげくアントロポセンなるものまで生み出してしまった人類は、正直終わっているし終わりでいいのではないかと私などは思ってしまうこともあるのですが、『野豚物語』に感じるのは私たちがいかに近代の支配下にあるかを順を追って解きほぐしていく作者の丁寧な手つきと「私たちはそもそもどこで間違えたのだろう」という問いを決して手放さない思慮深さでした。
自然破壊も資本主義も人間が人間のより良い未来のために遮二無二がんばってきた結果なのであって、それが外でもない人類を追い詰めているのだとしたら、人間が人間を利するために何かを頑張ること自体がそもそもの間違いだったとするのが妥当なのではないか……だとすると人間は人間以外のものを利する努力をいい加減本気で始めるべきなのではないか……愛玩動物として美的に配置されたポスターの犬たちの眼差しと無言は、動物と人間の関係についての哀切な問いかけである一方で、その堂々たる「私たち犬です感」によって動物と人間との関係に先立つ「動物の実存」を強烈に訴えてくるものでもありました。
『野豚物語』では猪は復讐を果たしはしますが「殺す相手を間違えて」しまい、結局何も起こせずに終わります。徹底的に虐げられ搾取されてきた動物たちが人類を打倒することは少なくとも作中ではありませんでした。猪に心を寄せるあまり矢も盾もたまらず渋谷の街を駆け出す主人公の姿には、あまりに巨大で強固な「近代」に対する作者の苛立ちと、これは生半可なことでは覆らないという透徹したリアリズムが反映されているように思います。しかし同時に「せめて一矢報いなければ」という強い意志と、変革へのなけなしの希望も間違いなく示されているのであり、私が本書の表紙の犬たちに感じるのもこのようなことでした。
私たちのアイディアを真摯に受け止め画像の使用許可を下さった漢聲出版社と、同社とのやりとりを誠実に仲介して下さったMangasickのゆうさんと黄さんに心からの感謝を申し上げます。前衛的で、実直で、愛らしい、本当に素晴らしい本になりました。著者の川勝さん、装丁の森さんからも、台北の皆様にくれぐれもよろしく、と言付かっております。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
真的是非常的感謝!
(編集部・中川)