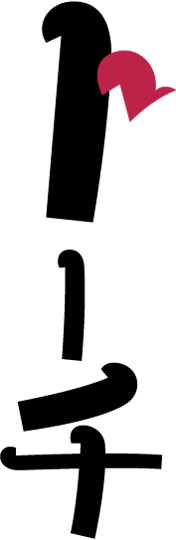川勝徳重氏の『電話・睡眠・音楽』、私は誤植を出してしまった。p.278『冬の池袋、午後5時〜6時まで』最終ページの最後のコマ、永美太郎さんのセリフ「IKBはサグ・シティーやな〜」が「IKBはザグ・シティーやな〜」になってしまっている。私が校正時に見落としたのだ。川勝氏、永美氏、そして読者の皆さん、申し訳ありません。永美氏は「サグ・シティー」と言った。これを読んでくださっている皆さんは脳内変換のほどよろしくお願いします。お手数をおかけして本当に申し訳ない。面目ない。
誤植の責任はすべて担当編集者にある。校正に時間をかけられなかった、複数人で回覧したのに全員見落とした、体調がすぐれなかった、言葉を知らなかった……一切の言い訳が通用しないのが誤植だ。「それもこれも全部お前が悪い」で終了。ノーマネーでフィニッシュです(高円寺になんでんかんでんができましたね)。私は大学を出て出版社で働き出して15年、大小様々、色とりどりの誤植を出してきた。本ができ上がった後に見つかる誤植から受ける心のダメージは今も昔もひどい。見つけた瞬間、心臓が踊り上がり、頭から血の気が引く。白目をむき、何も見えず何も聞こえなくなる。そのうち遠くの方から自分の心臓の音が聞こえはじめ、徐々に意識が戻ってくる。気を取り直し、最初にやることは誤植と思われる文字を見つめることだ。凝視する。「直れ」と思う。直らない。観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、念じる。直らない。指でこするなどして少し温めてみる。直らない。
次に誤植でない可能性を探ってみる。サグ・シティーのサグは「thug」と書く。英語の発音としてはサグではなくザグの方がむしろ正しい可能性がないとは言い切れない。「詳細・細部」を意味する「ディテール」という言葉がある。英語の「detail」をカタカナで表記したものだ。立風書房の雑誌編集部にいた頃、私が記事中に書いたディテールという表記を副編集長にすべて「ディティール」に直されて頭にきたことがある。「detail」はどう考えても「ディテール」ないし「ディテイル」でしょうが。「パンテー」を「パンティー」とか「テーカップ」を「ティーカップ」とすることのナウさに寄りかかり、何の考えもなしにテーをティーに置き換えているから「ディティール」などという素っ頓狂なことになるのだ、私もまだ23〜24歳で若かったから、そんなようなことを面と向かって言い放ち、つかみ合いの喧嘩になったことがある。それと同じで「thug」についても、私も皆もサグサグ言ってはいるが、実はきっと「ザグ」が正しいのだ。辞書で「thug」の発音を調べる。[θˈʌg]とある。前歯に舌を軽く押し当てて発声してみる。サグ。もう一度、ゆっくりやってみる。サァグ。ネイティブになりきってやってみたらタァグァッみたいになった。私としてはどうしても「ザグ」が正しいことにしたいのに。辞書を書き換えたい。スタジオジブリの「ジブリ」は「ghibli」で、イタリア語でサハラ砂漠に吹く熱風を意味する。本来の発音は「ギブリ」だが、宮崎駿が「ジブリ」だと思い込んでいた。途中で間違いに気づきはしたが、そのまま世界的に膾炙した、というのは有名な話だ。今「スタジオギブリが正しい!直せ!」と目くじら立てる人はいまい。もともと間違いだったものが「本当」になっていくメカニズムには創作の神秘と浪漫が詰まっている。社会通念や法律・経済といった、いわゆる「現実」と呼ばれるものが創作物のあり方を規定するように言われることが少なく無いが、優れた創作物はむしろ現実の方を規定するものだ。つまり科学とは別の何かだ。科学とは別の何かとは神通力のことだ。観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄、念じてみる。直らない。該当ページを両手で優しく挟み少し温めてみる。直らない。本当に直らない。
誤植に誰も気づかなければいい。誰も気づかなければ無かったことにできる。この私が気づかなかったのだから、他の人も気づかないはずだ。1つのフキダシだけをクローズアップするから濁点がことさら目に入る。漫画には必ず時制がかかるのだから、台詞のつながり・コマの流れに身をゆだねてみれば、こんな小さな濁点など目に入らないはずだ。2〜3ページ戻っては読み戻っては読みし、まるで初見のように該当箇所に「行き当たる」ということを繰り返す。ザグ、と書いてある。ザ、だ。ザである。どれだけ頭を空っぽにしても濁点を見落とすことができない。明朝体なので筆の入りと止め、それはそれはきれいな水滴形が2つ。ルーペで見るとその端正さがより際立ちますね。美しい。この国の印刷技術は本当にすごい。日本人として誇りに思う。まことに天晴れ。「切腹 やり方」で検索してみる。
今まであまり意識せずにきたが、「責任を果たす」と「責任を取る」は意味が違うらしい。「責任を果たす」は任務や義務を最後まで遂行することを言い、「責任を取る」は、失敗や損失に対しての責めを負う=引き受けることを言うようだ。私は今回、編集者としての責任を果たすことができずに誤植を出したので、その責任を取らなければいけない。お詫びと訂正を速やかに公開し、重版時に確実に修正することを宣言する、という儀式を粛々と行うわけだが、しかし、これで私は誤植の責任を「果たした」としても「取った」ことになるのだろうか。上司からドヤされ同僚から笑われ、著者に失望され、読者を混乱させ、自分が情けなくて泣く。15年間そんなことをずっとやってきて、答えは宙ぶらりんのまま時が流れた。今こうしている間も時は流れていく。二度と誤植を出さないことを誓えるかと問われればまるで自信がない。私が頭を丸めようが腹を切ろうが職を失おうが誤植は直らない。本の寿命は私よりも長い。私の死後、未来の読者に、自分すごい反省してますんでこの辺で勘弁してつかぁさい、詫びることすらできない。ここで早くも私の知性は底を打つ。一体どうすればいいのだろう。
アパートに戻って畳に寝ころぶ。網戸越しに入ってくる風が冷たい。虫が鳴いている。ひと雨ごとに秋が深まるなあ。ぼんやり天井を眺め、目目鼻口、あそこのシミは何だか人の顔に見えるぞ、などと独りごちていると涙が出てきた。
扇風機の台にしている古本の束をぼんやり眺める。ムージルの『寄宿生テルレスの混乱』が目に入った。面倒くさくて読んでいないやつだ。いつ買ったのかも覚えていない。「若旦那トクシゲの献身」という言葉が頭をよぎった。文字数もぴったりだし、韻も踏めている。混乱と献身。はは、うまいね。座布団一枚。献身。献身? なんで今そう思った?
2014年の秋(だったと思う)、川勝氏はコミティアの出張編集部にふらりと現れた。夕方になり、そろそろ撤収作業を始めるタイミングだった。「意志強ナツ子さんが行け行けって言うんで来ました」と言っていた。『十代劇画作品集』の巻末で、夏目房之介氏が川勝氏の第一印象について「ディレッタント」「若旦那」と書いていたが、本当にそんな感じであった。『怪奇短編劇画集 蝸牛』を持ってきてくれ、それに収録されている氏の「首猫島」を読んだ。私が作品について何かを言う前に、彼は水木しげるの絵柄の変遷について詳細な説明をし、それに対してやはり私が何か言う前に「あの、あれです、ヌーヴェル・ヴァーグをマンガでやりますよ」と言った。その時の私は「60年代のフランス映画っぽい、スタイリッシュなマンガを描きますよ」という程度の意味に捉えていた。20ページくらいの読み切り作品を、という話をしたように思う。「3ヶ月くらいで描きます」とのことだった。
冬が来て、年が明け、春。川勝氏のことを半分忘れかけていた2015年3月26日、「トーチ五輪(第2夜)」が開催されたアップリンクに氏が来ており、「すみません、やってます」と言った。
5月、新作の構想が送られてきた。全13話、300ページに及ぼうかという長編だった。パスカル・ラバテ、西村ツチカ、blue noteの1500番台、和田誠、ゴダール「気狂いピエロ」、トリュフォー「突然炎のごとく」、ヒッチコック「北北西に進路をとれ」、ロバート・ボイルの美術セット、板倉建築事務所、青山二郎……絵柄について、また各話のプロットについて、無数の引用例が想起させるディテールが、それがどんな作品かを何よりも雄弁に語っていた。すでに一つの作品を読んでいるようだった。重要なキーワードの一つに「テロ」があった。ぞくぞくした。
——
新宿御苑の近く、小規模なデモが起きているのを傍目にみます。
しばらく考え事をしていたら突然銃声が起きます。
デモ隊へ、警察のほうが発砲をしたのです
わたしのイメージでは1905年にサンクトペテルブルクで起きた血の日曜日事件と重ねております。
逃げ惑う人々の中、驚いた主人公は急に倒れ込みます。
視界がどんどん消えてゆき……
——
さらに季節がめぐり、その間、彼は山田参助氏のアシスタントに入ったりしているようだった。新作については「苦労している」「作画にひどく時間がかかる」「大学院が…」「見通しが立たない」というもので、7月に入り、あまりにも目処が立たないので、代わりに……という前置きとともに「固まりミルク」という過去作を渡された。「授業中にオナニーして校内謹慎になったアホな中学生が三人おりまして、彼らを励ますために書いた漫画です。80ページです。3日で書きました」。いや、別にいいんだけど、なんなんだろうと思っていたら、月末に新作のネームが送られてきた。「電話・睡眠・音楽」という仮タイトルがついていた。最初の長編とはまったく別の形になっていたが、作画方法や都会的な雰囲気は当初の構想を踏まえたもので私は感激したし、なにより新作の見通しが立ったことを喜んだ。川勝氏も晴れやかな表情だった。
しかし、それから実に丸1年、新作はできなかった。
川勝氏は時々メールをくれたが新作の進捗については謎だった。きっと諦めたのだろう。私の過度の期待がプレッシャーになってしまったのだろうか、本人も自分に課すハードルを上げすぎてしまったのかもしれない。仮に諦めたのだとしても何ら責められるべきではないし、20歳そこそこの若者が貸本劇画やガロの手法を忠実に再現した、質の高いヴィンテージ作品を手掛けるだけでも商業出版として十分勝ち目がある。そんなふうに考えるようになっていった。
2016年8月25日の夜、唐突に『電話・睡眠・音楽』52ページが送られてきた。
「ようやく完成しました。随分と時間がかかりましてすみませんでした。なんだか、自分では、これが面白いのかどうなのか、サッパリわかりませんが……」と書いてあった。
読んだ。驚いた。彼は最初に「ヌーヴェル・ヴァーグを」と宣言して以来、ずっと一人で戦いつづけていたのだ。新しい人が出てきた、と思った。原稿を1枚1枚繰りながら、今すぐ川勝くんのもとに走って行って100万回のキスを贈りたい気持ちだった。電話でそう伝えたらキモがられた。
ヌーヴェル・ヴァーグはフランス語で「新しい波」という意味だそうだ。ゴダール『映画史』の帯だったか、エスクァイア・マガジンの白い分厚い本だったか完全に忘れたが、とにかくゴダールの関連本で、日本の映画監督だったか作家だったか誰だったかこれも完全に忘れてひどいが、ヌーヴェル・ヴァーグのことを語っていた。パクれ、切りまくって貼り合わろ、オリジナリティなどなくても優れた作品ができることをヌーヴェル・ヴァーグが証明してくれた。このことに若い作家たちがどれだけ勇気付けられたことだろう、と。手元に資料がないので正確なところはまるで自信がないが、こんなようなことが確かに書いてあった。
「電話・睡眠・音楽」という作品自体がそうであったように、公開後のメディアでの取り上げられ方もセンセーショナルなものだったから、私も川勝氏のことをいつの間にか「ユースカルチャーの旗手」という目で見るようになっていた。しかし、単行本の編集過程でその印象が大きく変わっていった。1冊分、繰り返し通読するうちに、この人は誰からも頼まれていないのになぜこんなに自分で勝手に苦労を背負い込んでいるのだろう。と思うようになった。泥くさいとすら思った。貸本劇画やガロが泥くさいのでは決してなく、氏がこれまでに積み重ねてきたもののその「量」が、である。描いた量、知識の量、考えた量。量は時間だ。今回の作品集では自身が長い時間と膨大な手間暇をかけて習得してきた技法、そして先達の作品に対する解釈の様式を、全くもったいぶることなく披露している。もし私が漫画家なら自分が苦労して掴んだ奥義は隠しておくに違いないが、彼は、誰もが閲覧可能な形で、惜しげもなく差し出している。
この姿勢に私は氏の「献身」を感じる。誰に対する献身か。「天才ではない全ての漫画家たち」である。才能より熱狂を、霊感より圧倒的な知性を。勉強しろ、私の作品をパクれ、切りまくって、貼り合わせろ……そんな声が聞こえてくるようだ。川勝徳重は、今この時代に生きる一人の若者として、誰もが聞き取れる形で、最初にその声を上げた人なのではないか。先にも書いたが「ヌーヴェル・ヴァーグ」とは「新しい波」のことである。波が起きるには最初に風が必要で、川勝氏本人と小西康陽氏が言うその言葉の射程は、波そのものだけでなく、「波を起こした最初のもの」、そして波が長距離を渡り時間をかけて大きくなった先の「うねり」まで捉えている。
今2018年9月27日(木)23時50分、ここまで書いたところで川勝氏から電話が。
200ページ「赤塚藤雄の頃」タイトル
誤:文集文庫
正:文春文庫
泣きそうです。正誤表出します。
(トーチ編集部・中川)