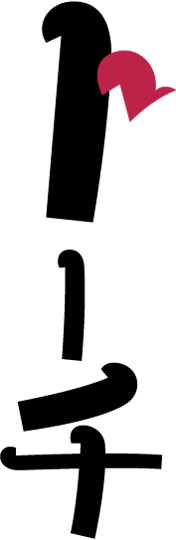「フルカラー&フルアナログ作画、原画総枚数約700枚、執筆5年に及ぶ破格の超大作」と帯に書いた。私はこの文句を10分くらいで書いたのだし、10秒もあれば読み終わる短文であるが、ここに書かれていることがいかに特別なことかは強調しすぎてしすぎることはない。今、商業マンガで「こんなこと」をやっているのは、おそらく赤瀬由里子ただ一人だ。
本作第1話が掲載されたのが2020年1月だった。これは世界中でパンデミックの恐慌が始まったのと全く同時期である。本作で描かれる原因不明の難病「昏睡病」と新型コロナの共時性に作者も私も驚き、狼狽えた。本作は話が進むにつれて「美しい夢と過酷な現実、どちらが生きるに値するか」という問いが浮き彫りになっていく。この問いは連載準備の段階からすでに本作の背骨にすえられていたが、パンデミックが現実のものになった時、今まさに不安に苛まれ病に苦しんでいる人たちを前に、その問い自体が意味を持ち堪えることができるのか、という新たな問題が突然立ち現れた。
美しい夢と過酷な現実どちらをとるか、「現実一択だ」と作者は直観している。私もそう思う。しかし未来に何の希望も持てない状況で、どうすればこれを説得力をもって伝えることができるか……このことに作者がどう向き合い、悩み、結論を出したかはぜひ本作を最後まで読み、その目で確かめてほしい。時代がどんなに殺伐を極めようとヒューマニズムへの信頼を手放さなかった作者の姿勢に私は感動する。
冒頭の帯文の話に戻るが、前作『サザンと彗星の少女』から本作『ナイトメアバスターズ』と、ほとんど無尽蔵とも思える作者のエネルギーは一体どこから来るのだろう。私は商業漫画の編集者であるから、彼女の「このやり方」がいかに法外なものかをよく知っている。もし今、誰かが彼女と同じスタイルで連載を始めようとしたら間違いなく私は止める。商業連載で、量産とは対極にあるこのやり方で、長編を描ききることは普通できない。しかし赤瀬由里子は、やる。
第23回手塚治虫文化賞(2019年)の候補作に前作『サザンと彗星の少女』があがり、みなもと太郎と里中満智子が講評で同作に触れている。
「マンガを描く喜びの原点がある」(みなもと)
「描く楽しみ(苦しみも当然あるが)を知る作者だからこそ生み出せた世界だと思う」(里中)
みなもと先生は後日、雑談でこうもおっしゃっていた。「これ読むとね、マンガを描くのが楽しくてしょうがなかった頃のことを思い出すんです」。『サザン〜』はこの回の受賞を逃し、他の選考委員の講評も含め同作に言及された箇所はこの数行のみだったが、偉大な先達が「描く喜び」「描く楽しみ」という言葉を口にしたことに私は衝撃を受けた。
「偉大な先達」と言う時、マンガ文化を切り拓き大きく育ててくださったご功績に……とか、後進のために尽力してくださり……とか、巨匠たちの「献身」にばかり気持ちがいくが、それは彼らの画業の結果であって出発点ではない。どんなマンガ家にも多分「マンガを描くのが楽しかったその時間」があって、それがなければ誰も出発しえなかったことを、マンガを描かない私は想像したことがなかった。みなもと先生や里中先生が「描く喜び/描く楽しみ」と口を揃えるということは、もしかしたら手塚先生やさいとう先生にもそんな時間があったのかもしれないと想像してしまう。それがいつでどんなものだったかは誰にもわからないし、おそらく本人も正確に振り返ることはできない。マンガを描く喜びはきっと、夢中で手を動かしている「その時・その身体」にだけ宿るものだ。
マンガ制作におけるAIの議論は、技法、作家の思考様式、経済、権利……どこをとっても緊急性が高く、マンガ家にとっても出版社にとっても重要なものだ。一方で「先人たちが感じていた(らしい)『マンガを描く喜び』をAIを用いてどう描き手の身体に再現するか」は議論にならない。議論にならないだけで、それは、ある。でないと『ナイトメアバスターズ』が今この形で手元にあることの説明がつかない。赤瀬由里子の作品から溢れ出る「マンガ、大変だけど楽しい」は、懸命に手を動かし続ける者にのみ与えられる宝物だ。そしてそれを大いに喜び高らかに謳歌する彼女の作品は、そのまま先人たちへの感謝の証であり、そしてマンガそのものに対する祝福だと私は思う。
(編集部・中川)