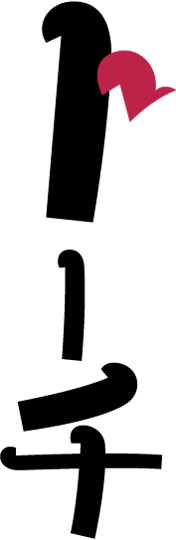斎藤潤一郎『死都調布 南米紀行』が4月10日に刊行される。
4月5日から書き始めて、今4月6日深夜。7日に緊急事態宣言が出るそうだから本稿はその後に読む人が多いと思う。緊急事態が宣言されてもされなくても私の言いたいことは変わらない。
疫病の時代である。人と会うこと、集まること、話すことに後ろめたさがつきまとう。外に出ることもできなくはないが一層しづらくなるだろう。諍うことも愛することも今までどおりのやり方とは変わってくるのかもしれない。禁じられてそうなるか自主的にそうするかは問題ではなく、今まで当たり前にできていたことが少しずつ減ってきている。事態が終息すれば失われたものが元に戻るかというと多分そんなことはなく、戻るものもあれば取り返しがつかないものもある。私たちが今何を失いつつあるか、それがわかるのは多分もっとずっと後のことだ。何とも頼りなく寂しいことだ。
私の周囲からも櫛の歯が欠けるように人がぽつぽつといなくなっている、気がする。これは感染者が続々と隔離されているということではなく、自社と他社の業務の仕組みが急速に組み替えられていく中で、人の行き来が物理的に減ってきているということだ。出入りの業者が、他社の同業者が、近所のコンビニ客が、高円寺の酔客が、予告なく静かに姿を消している。私のまわりから彼らの姿が消えていくのと同じように、私も誰かのそばからひっそりと姿を消しているのだろう。
協働する人々の身体が近くになくなるというのは、電話とメールが苦手ですぐ対面で事を進めたがる私のような人間にとっては普通に難儀なことである。モニターでのpdf校正だと目がだだ滑るので紙のゲラが必須だし、ちょっとしたことでもすぐに近くの人に聞きがちだし、打ち合わせや原稿取りに乗じて漫画家と茶飲み話をしたい。私は現在従来のやり方からテレワークに移行しつつあるところだが、これが完全なテレワークになっても編集の仕事に支障はないどころか効率はむしろ向上するのだろう。しかし先に挙げたような様々な余剰なしにはどうにもやる気が出ない私のパフォーマンスは少しばかり低下すると思う。多い時には5日間で7回とか行くこともある福来門も今は閉まっているし。
國破れて山河在り
城春にして草木深し
時に感じては花にも涙を濺ぎ
別れを恨んでは鳥にも心を驚かす
峰火三月に連なり
家書萬金に抵る
白頭掻けば更に短く
渾べて簪に勝えざらんと欲す
先週来、帰り道で口をついて出るのは杜甫の「春望」とASA-CHANG&巡礼の「日の出マーチ」である。「國破れて山河ありなことだよ…」という感傷と、「十(とお)でとうとう花が咲いて大笑い、つれづれに暮らすニッポン!とくらあ」みたいなやけっぱちの清々しさを交互に噛み締めながら春の夜道を歩くのも乙なものだ。杜甫とピエール瀧に感謝したい。
「漫画なんか描いている場合じゃない気がして」。先週と今週だけで担当作家が3人同じことを言った。たしかに。漫画がなくても人は死なない。毎日人が死に、自分や身近な人々にも明日何が起きるかわからない中で、もう誰も振り向いてくれないのではないかという不安や、今まさに苦しんでいる人たちを助けることができない無力感が胸をかすめ、ペンを持つ手が「うっ」と止まるのだと思う。
私は漫画家だったことはないけれど、思い当たるフシがなくもない。東日本大震災の時私は無職生活3年目で、毎日ひたすら家と図書館を往復していた。貯金額から逆算し1日に使っていいのは200円までという自分で考えたルールを嬉々として守り、慎ましくも満ち足りた日々を送っていたところへあの一連の映像と情報が押し寄せてきた。金も稼がず、何の役にも立たず、日々いそいそと自分の弁当など拵えたりして、私はいったい何をやっているのだろう……焦慮にずぶ濡れ、日がな一日ツイッターのタイムラインにへばりつき、増え続ける死者を数え上げては疲れ果て腹を下していた。
かなり長いこと続いた下痢が止まった時のことは今でもはっきり覚えている。神西清の「チェーホフ序説」を読んだのだ。緩みっぱなしの腹をさすりさすり岩波文庫の『カシタンカ・ねむい 他七篇』を読んでいたら巻末あたりに収録されていたのでやはり腹をさすりさすり読んだ。チェーホフが医師であったことは有名だが、一方で大変非情な人間だったということが書かれていた。今、青空文庫で読めるので確認したところ、私の下痢を止めたのは4章の最後、ロシア飢饉(Wikipediaによれば37万5000人が死亡したという)に際してチェーホフがどう振る舞ったかを記した部分だった。
かいつまむとこうだ。1891年から翌年にかけてロシアで大規模かつ悲惨な飢饉が起きた。未曾有の危機に臨み気合いの入った救民事業をぐんぐん推し進めるトルストイの「勇敢と権威」に大いに感銘を受けたチェーホフは、医師として、また文士として立ち上がる。友人たちに私信を送って義捐金を募り、農民のために馬を手配、ルポルタージュを書くべく各地の視察と取材に赴いた。しかし義捐金はあまり集まらず、馬も思ったほどの効果を見せなかった。そしてルポルタージュに至っては結局1行も書いていない。新聞社の社主・スヴォーリンを伴い取材旅行に出てはみたが全然やる気が出なかったらしい。スヴォーリンからの度重なる原稿催促に対し、チェーホフはこう返信している。「二十回も書き出したのだが、その都度そらぞらしくなって投げだした。結局ぼくは君(スヴォーリン)と一緒に漫然と旅行して、漫然とピローグを食べただけのことらしい。但しあのピローグはうまかったね」。
獅子奮迅の活躍を見せるトルストイを「神のようだ」とあがめ、大いに奮い立ち、各地を視察して得た結論が「あそこのピローグはうまかったね」である。非道い。
非道いがしかし、当時の私はこれを読んで泣くほど笑い、憑き物が落ちるというか、ハタと正気に戻るというか、そんな感じがした。事実、下痢は止まったのである。人の非情さに救われる。これは一体どういうことだろう。普通、人の苦しみを癒すのは人の優しさではなかったか。
ドイツ政府は「アーティストは今、生命維持に必要不可欠な存在」とし、芸術家やフリーランサー、個人事業者に対する手厚い支援を決めたと前にニュースで見た。一方、本邦では布マスクが2枚配られるらしく私はボヨヨン(目が飛び出す音)、ドイツも日本も同じ敗戦国なのにどこでこんなに差がついたのだろうと思わずにはいられないのだが、それは今は置くとして、なぜ芸術家が我々の生命維持に必要不可欠なのかを改めて考えてみると、芸術家が生み出す作品が人々を励まし心を癒すことができるから“だけではない”気が私にはするのである。
スティーヴン・キングが著書『小説作法』の中で、「作品のテーマとは作家が述べる人間の条件についての声明」だと書いている。条件というからには制約の形をとるのだろう。つまり「〜だから人間だ」ではなく「〜でないものを人間とは呼ばない」ということだ。「私は人間を血と糞の詰まった袋だと考える」という宣言と、「私は血と糞の詰まった袋でないものを人間とは考えない」という宣言とでは、後者の方が、何かこう、誰も頼んでいない面倒ごとに勝手に挑んでいくようなばか正直さがにじみ出ている気がするし、作品のエンジンとして力強いものになりそうな予感がしないだろうか……いや、すみません、ちょっとわかりません。何が言いたいのか自分でもわからなくなってきた。まあ何でもいいのだ。俺は他者の痛みを理解できぬものを人間とは呼ばない、という作家もいれば、私は悪事をなさぬものを人間とは呼びません、という作家もいるだろう。同じ作家でも作品によって「〜」に入るものも変わってこよう。スティーヴン・キングは小説家と小説について書いてはいるが、小説を芸術に、小説家を芸術家に置き換えてもそれほど見当違いではないように思う。「芸術家」というと何だか立派な、崇高な存在と捉える人もいるかもしれないが、私はそうは思っておらず、その辺については以前書いた「何となくうまくいかない新人漫画家にやってみてほしい5つの裏技」という記事の2項目で少し触れているので参照してほしい。言わずもがなだが、商業作家・同人作家を問わず漫画家も芸術家である。
私は自分のことを人間だと思っているのだけど、どうしてそう思えているのだろう。どうもDNAと教育だけでなく、芸術家とその作品に多くを頼っている気がする。私はヒトのDNAを持ち高等教育まで受けたにも関わらず、震災の悲惨さをテレビで見た途端、心?精神?に何か決定的な穴が空いた。下痢は腹だけでなく知的・情緒的にも起きていたように思う。どこかにぽっかり空いたその穴から人間として持ちこたえるために必要な燃料がちょろちょろと漏れ出て行く感じだろうか。情報、金、絆がこの穴を埋めるものと私は思いこんでいたがそうではなく、穴を埋めてくれたのはチェーホフの非情さと神西清の研究者としての熱狂だった。危機に臨んで空いた穴を埋めてくれるのは必ずしも芸術家の前向きさや優しさではないことを私は知った。厄介なのは、どこに穴が空いたのか、また自分がどんな補修材を必要としているかは偶然穴が埋まってみるまでわからないということだ。いつ何が起きてもいいように備えるならば、それが役に立つかどうかはわからなくても、材質も大きさも、とにかく多くのバリエーションが確保されいつでも手の届く所に置いてある必要がある。バリエーションは多くて多すぎることはない。私たちの生命維持に必要不可欠な芸術家の生命維持に必要なものを速やかに供給することは公共のインフラを維持するのと同じ意味を持つと私は思う。
このことはおそらくドイツ人にとっては人間に水が必要なのと同じくらい自明のことなのだろうが、私たちはとても忘れっぽいからいつも何度でも確認しておく必要がある。インフラが縮小・独占された世界がどんなものかはもう皆知っているはずだ。怒りのデスロードが幕を開けるのである。そして我々は人間としての形をとどめていられず、やがて、死ぬ……END OF MEXICO……だから芸術家は沢山いていすぎることはなく、何の役に立つかわからない変な作品が沢山あってありすぎることはない。作品の出来不出来は関係ない。駄作か名作かの評価など時間でいかようにも変わる不安定なものだ。とにかく「色々ある/沢山ある」ということが大事だ。商業作家、同人作家を問わず今度の危機に「うっ」と手が止まっている漫画家がもしいたら、自分が水や食料や医療と同じようにみんなが生きるために必要なインフラの一端を担っていると考えてみると少し楽になるかもしれない。それでだめならトーチを覗いてみるといいかもしれない。読まなくてもいいからトップページをザッと眺めてほしい。色んな漫画家が色んな作品を描いている。そして色んな漫画家が色んな作品を描いているというその事実があなたを少し勇気づけるかもしれない。トーチにアクセスする前に手塚治虫、さいとう・たかを、ちばてつや、バロン吉元、つげ義春……先人たちの作品を読むのはなお良い。大きな戦争や幾多の災害を経験してきた彼らが最前線で踏み固めてくれた創作の道は磐石である。
私はここまで「芸術は役に立つから芸術家は必要だ」ということしか言えていない。役に立つとか立たないとか、そんなエクスキューズなど芸術の前には存在できないずなのに。これだけ長々と言葉を費やして何だこの体たらくは。もどかしい。おそらく芸術がなぜ必要かという問い自体がいきなりズレているのだ……クソが…
いつも通り出社して『死都調布 南米紀行』の見本が机に置いてあった時、私はギョッとした。自分で入稿と校了をしておいて、いざ立体物となったものを見ると一瞬それが何かわからなかった。なにか「うわ…」みたいな声を出していたかもしれない。恐る恐る手を伸ばすと、表紙の船が、髑髏が、背表紙の鮮烈な赤が、何か囁いている。耳をすますとはっきり聞こえた。「準備はいいか?」と。「何の準備ですか?」「旅の準備だ」「どんな旅ですか?」「GANGSTA JOUNEYだ」「それは何ですか?」「お前が決めるのだ…」
『死都調布 南米紀行』は『死都調布』シリーズの第二弾である。連載期間は2018年12月〜2020年1月「トーチweb」。途中、作者の斎藤潤一郎が階段から落ちて右手を怪我したり尿管結石で救急搬送されたりしたがいずれも回復した。全9話に描き下ろしカラー原稿16ページを収録した全280ページ。巻末には前作『死都調布』と次回作『死都調布ミステリー・アメリカ』の予告が載っている。前作と同様カバーはなく本体表紙と帯のみ。表1のタイトルロゴ・背・表4の赤はDIC118、本文1色ページはDIC F195。装幀は鈴木哲生。p75、p106、p174、p275に、前作では描かれなかった「女の涙」が描かれている。「男の涙」が描かれているのはp129、p205、p231。前作では逃げ場のない孤独と身体的な痛みを感じた男たちが泣いていた。本作では異国の風景(動物)を前にした男が涙を流している。
「夜の果てへの旅だ。準備はいいか? 斎藤潤一郎『死都調布 南米紀行』を読む」と題された本稿は、一文字めから徹頭徹尾『死都調布 南米紀行』を不特定多数の人々に勧めるために書かれたものだ。読者は冒頭から長い余談が続いたように思ったかもしれないがそうではない。その証拠に本稿に出てくる「芸術家」を「斎藤潤一郎」に、「芸術」と「芸術作品」を「死都調布南米紀行」にそっくりそのまま置き換えても成立する。そのように書いてある。最初からそうしようと思っていたわけではない。最初からそうしようと思っていたことにしようと、今自分で決めたのだ。本当は普通に「本作はこういう内容で、こういった魅力があるので読んで下さい」というオーソドックスなコマーシャルを想定していたのだが、この作品に関してはそういう書き方があまり意味をなさない気は最初からしていた。まあ書いてるうちにちゃんとコマーシャルふうになるだろうと思って書き始めたものの、結局どうにもならなかった。
作品を人に勧めようという時に「本作について語るべきことは何もない。ただ読むべし」の一言で足ると思えるほど私は楽観的ではないし、圧倒的な作品を前にして沈黙できぬなら更に万言を尽くして七転八倒するべきだとも思う。しかし前者は虚しいし後者は苦しいのでどちらもやりたくない。どうしたものかと書いたものを読み返す中で自分が何を書いていたかを発見したのである。繰り返しになるが、本稿における芸術と芸術家についての記述は全て斎藤潤一郎と『死都調布 南米紀行』についての記述でもある。
深夜3時
異国の町で私は夢想する
あの獣に共鳴するように
表紙をめくると始まるイントロダクションだ。本作を読むことはそのまま旅に出ることである。比喩ではない。読者は読み終わる前と後で同じ人間ではいられない。賭けてもいい。「深夜3時/異国の町で私は夢想する」……これを読んだ時、私の頭の中で旅の始まりを告げる音楽をたしかに聞いた。初めて本書を開いた人々がそこにどんな音楽を聞いたか教えてもらうのが今から楽しみでならない。ちなみに私にはハービー・ハンコックの『Maiden Voyage』が聞こえた。同じ旅程でも旅人が百人いれば百通りの旅になるように、この作品を読み終えた者は誰もが「私だけの体験」をするのである。本書と初めて遭遇した時に私が聞いたところによれば、これがどんな旅かは読者が決めるらしい。各自必要なものを見極め旅支度をせよということだ。私は本作で描かれる夜景にいかんともしがたい旅情を感じた。本書に描かれる夜の果てまで、他でもない本書に連れ出してもらいたいと思った。
『夜の果てへの旅』はセリーヌの代表作である。セリーヌはフランスの作家で、痛ましいほど露骨なリアリズムで描かれた怒りと呪詛に満ちた作品で絶大なインパクトを残した一方、戦時下のフランスで反ユダヤ的な評論や政治的パンフレットを数多く書き、国家反逆罪の疑いで逮捕状が出され亡命生活を送らざるをえなかった(ほぼWikipediaコピペ)という色々大変な作家である。『夜の果てへの旅』はゴンクール賞の候補作にもなったらしいが読むと本当に非道い。チェーホフの「あのピローグはうまかったね」とも通じる何かが全ページにわたって叩きつけられている。非道すぎて笑うしかなく、笑いがすぎると真顔になる。後半は概ねこの新しい真顔で読むことになるが、読み終えて本を閉じる時に思うのは「なんかヤバイものを読んでしまった」である。今思い出したがセリーヌもチェーホフと同じく医師であった。彼の墓石にはただ一言「NON(否)」と刻まれているらしい。
夜の果ては朝だろうか。セリーヌの『夜の果てへの旅』ではそうではなかった。夜の果ては朝ではなく霧すら立ち込めるより濃密な夜だった。『死都調布 南米紀行』は私たちをどこに連れ出すのだろう。難儀な時世ではあるがどなたも良い旅を。くれぐれもお気をつけて……
(編集部・中川)